創薬開発の革新的な技術として期待
同志社大学生命医科学研究科の齋藤直人准教授らのグループは14日、特異的かつ高速なcAMP生細胞イメージングを可能にする蛍光プローブ『gCarvi』の開発に成功したと発表した。
薬の効果を評価する上で目的細胞のcAMP動態を可視化できるgCarviは、創薬開発における革新的な技術として期待される。
さらに、齋藤氏らは、ニューロンのcAMP濃度の設定値(全体指令)によって、神経回路の活動レベルが制御されていることや、cAMPシナプス前部ドメイン(個別指令)が、シナプス可塑性におけるシナプス特異性を規定している現象を蛍光動画解析(蛍光イメージング)によって明らかにした。
生物の個体や組織では、全体として情報を共有するだけではなく、その一部分だけで情報を扱う仕組みを適宜活用することで、それぞれの機能を維持している。
一個の細胞もシステマティックな工場のようなものであり、細胞全体で情報を共有する場面や、一部分だけに情報を集約する仕組みを活用していると考えられる。
細胞体から役割分担の異なる複数の神経突起を長く伸ばす脳を構成する神経細胞(ニューロン)では、細胞全体/一部分の情報管理を適切に行うシステムを、高度に発達させていると予想できる。
たとえば、細胞外から受け取った情報を細胞内に伝えて応答するために、細胞内で最初に情報を伝える役割をセカンドメッセンジャーと呼ぶ。このセカンドメッセンジャー分子の指示に基づいて、細胞は様々な分子を動かし、適切に応答する。
歴史的に最初に発見されたセカンドメッセンジャー分子が、サイクリックAMP(cAMP)である。cAMPをセカンドメッセンジャーとして活用する細胞は、原核・真核細胞問わず広く存在することが知られている。このcAMPを用いた指示の仕組みとして、細胞全体に渡るような全体指令に加えて、一部分にだけ行う個別指令がある可能性については、仮説(マイクロドメイン仮説)として1980年代に提唱された。
cAMPが指示を行うためには、細胞内の指示を行う場所でcAMP濃度を上昇させる必要がある。
今回、齋藤准教授の研究グループでは、細胞内のcAMPの濃度変化を可視化できる蛍光プローブ“gCarvi(ジーカービィ)”を開発した。
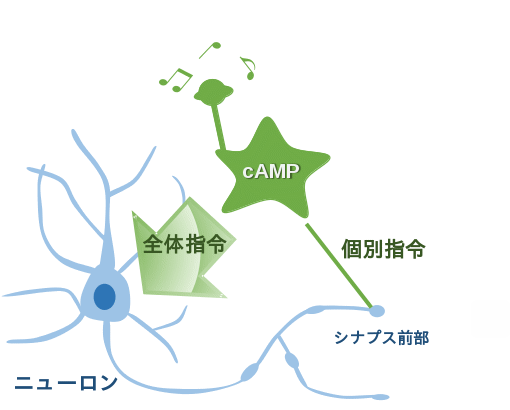
さらに、このgCarviをニューロンに発現させることで、①「cAMP全体指令によって、神経回路の活動が高まる」、②「cAMP個別指令によって、シナプス前部が活性化する」ことを蛍光動画解析(蛍光イメージング)によって明らかにした。これらの解明は、これまで仮説に止まっていたcAMP個別指令が実際に存在することを、はっきりと示した初めての報告である(図1)。
生きた細胞内で生じる分子の動態を、可視化する手法として、蛍光イメージングは欠かせない研究手法となっている。セカンドメッセンジャーとして機能するcAMPは主要な細胞シグナリング分子であり、脳の老化(認知機能低下)や免疫・炎症反応、ホルモン応答などにも関与している。
重要なシグナリング分子であるにも関わらず、その動態を解析できるような可視化ツール(蛍光プローブ)の開発は世界的にも進んでいない。
そこで、齋藤氏らは、蛍光イメージング用のcAMPプローブとして、gCarviを開発した。gCarviは大腸菌のcAMP結合領域と、円順列変異型緑色蛍光タンパク質を融合した遺伝子発現型cAMP蛍光プローブだ(図2A)。
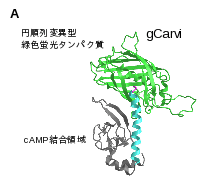
(A)大腸菌由来のcAMP結合領域に円順列変異型緑色蛍光タンパク質を融合させたgCarviの予想構造。
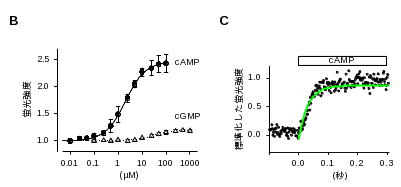
(C)カバーグラスに固定した精製gCarviタンパク質に、微小灌流装置を用いてcAMPを高速に投与したときの一例。cAMP動態を高速にイメージングできることが分かる。
gCarviは、①「分子量が小さい」、②「cAMPに特異的に反応する」、③「cAMP濃度の変化を高速にモニターできる」ーの3つの優れた特徴を有している。
gCarviは、cAMP蛍光プローブとして最小サイズであり、この点は実際に遺伝子発現する上で、哺乳類細胞に発現させやすい、つまり使いやすさに繋がる。
図2BにgCarviのcAMPとサイクリックGMP(cGMP)に対する容量反応曲線を示した。cGMPは哺乳類細胞がセカンドメッセンジャーとして利用するcAMPと構造が似たもう一つのサイクリックヌクレオチドであるが、gCarviはcGMPには小さな反応しか示さないことが分かる。
細胞内では、「cGMPは数µM程度までしか上昇しない」と報告されているため、現実的には「gCarviはcGMPには反応しない」といっても良いだろう。gCarviのcAMP応答/cGMP応答の比は100倍以上と見積もることができ、またその他のヌクレオチドには反応しない実態も確かめている。
既存のcAMP蛍光プローブの中で最高のcAMP特異性を示すgCarviを用いることで、正しくcAMP濃度変化を可視化できるといえる。
また、微小灌流装置を用いることで、gCarviのcAMPに対する結合速度を解析しました(図2C)。このような解析から、gCarviはcAMPが10 µM上昇する変化を、0.1秒以内の速さでモニターできることが分かった。この高速性はcAMP動態を実時間でイメージングする上で、重要なポイントとなる。実際に既存のcAMP蛍光プローブでテストを行ったところ、時間経過の遅延したイメージングになってしまうことを確認している。
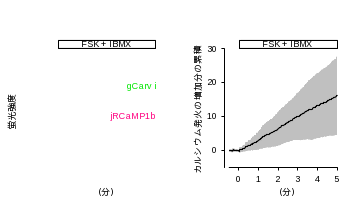
gCarviとjRCaMP1bを発現させた海馬ニューロンに、cAMP合成酵素活性化剤forskolin(FSK)とcAMP分解酵素阻害剤IBMXを投与することで、ニューロン全体のcAMPを上昇させると、Ca2+濃度上昇(左)と発火活動の上昇(右)が誘導された。
今回の研究では、gCarviとCa2+赤色蛍光プローブであるjRCaMP1bを海馬ニューロンに発現させることで、緑色蛍光でcAMPの、赤色蛍光でCa2+の動態を同時に解析した(図3)。
薬理学的にニューロン全体のcAMP上昇を引き起こすと、これに伴ってニューロン内のCa2+濃度上昇と発火活動の上昇が観察された。このような解析結果から、ニューロン内のcAMP濃度の設定値(cAMP全体指令)によって、神経回路の活動レベルを制御できることが分かった。
小脳顆粒細胞のシナプス前部は、cAMP上昇の下流シグナリングによって、長期的に伝達物質放出を促進するような可塑性を示す。そこで、1つ1つのシナプス前部のcAMP上昇率と、伝達物質放出の促進率を解析すると、シナプス前部毎にcAMP動態は異なっており、そのcAMP上昇率と伝達物質放出の促進率との間には、強い相関があることが分かった(図4)。
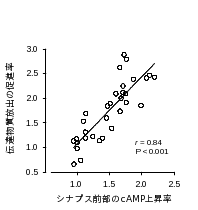
小脳顆粒細胞のシナプス前部では、様々な大きさのcAMP上昇が観察された。シナプス小胞を染めるFM色素を用いて、エンドサイトーシスしたシナプス小胞の量を解析した。この解析から、シナプス前部のcAMP上昇率と伝達物質放出の促進率との間には、正の一次相関があった。
cAMPの個別指令の方法として、マイクロドメイン仮説が提唱されている。cAMPが1µm3程度の空間に閉じたシグナリングを形成していることがあるのではないかという仮説である。
齋藤氏らは、cAMPマイクロドメインの一例として、シナプス前部という微小空間に閉じたcAMPシグナリング-シナプス前部ドメイン-を、cAMP蛍光イメージングによって明らかにした。この結果は、学習や神経回路の恒常性に寄与するシナプス可塑性が、cAMPシナプス前部ドメインによってシナプス毎に個別に制御されていることを示唆している。
様々な細胞応答を引き起こすGタンパク質共役型受容体(GPCR)は、創薬開発の世界では主要な標的分子である。
さらに、多くのGPCRは細胞内cAMP濃度を増加または減少させる。このようなcAMPの増減は、ELISA法などによるEnd-point assayを用いて研究されてきた。
脳内の認知機能を司る部位特定や薬効確認への活用も期待
gCarviを用いたcAMP生細胞イメージングでは、End-point assayでは見ることができない多様なcAMP動態の解析が可能である。微小空間に生じるcAMPシナプス前部ドメインも、End-point assayでの解析は困難であろう。薬の効果を評価する上で目的細胞のcAMP動態を可視化できるgCarviは、創薬開発における革新的な技術である。
一例として、認知症改善薬の開発に貢献できると考えている。老化やアルツハイマー型認知症による認知機能の低下の一因として、cAMPシグナリングの減弱が示唆されている。
cAMPの分解酵素を阻害することで、低下した認知機能が改善するという実験結果も報告されている。
だが、その細胞レベルの詳細は不明であり、脳内のどこのcAMPシグナリングが認知機能を左右するのか分かっていない。gCarviを用いたニューロンcAMP動態解析は、こうした問題に直接的にアプローチできるため、脳内の認知機能を司る部位の特定や薬効の確認など、創薬の現場において新たな一手として期待される。


