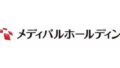ジョンソン・エンド・ジョンソンは8月11日、教育サービス「LEAPLE」を運営するBatonLinkと連携し、医療従事者を志す高校生を対象とした特別イベント「次世代医療人材シンポジウム」を医療従事者向けトレーニング施設のジョンソン・エンド・ジョンソン インスティテュート東京で開催した。
「人生100年時代」を迎えた現代社会では、これまで以上に健康・医療の重要度が増しているにも関わらず、日本はヘルスリテラシーに関する自己評価が諸外国と比べて最下位という結果が明らかになっている。

さらに、これからの時代を生きる高校生の教育現場において、ヘルスリテラシーに関する学習機会がほとんどないという現状も大きな課題となっている。
また、我々の健康・医療を支える医療現場については、医師届出数が過去最多を更新したにも関わらず、人口1000人当たりの医師数はわずか2.6人であり、世界水準を大きく下回っている。中でも、手術医療を担う外科医師数は減少しており、日本の医師全体の3.9%にとどまっているのが現状だ。

同シンポジウムは、ジョンソン・エンド・ジョンソン メドテックが推進する、ヘルスリテラシーを向上させ、一人ひとりが健康や医療との向き合い方を知り、行動することで、誰もが自分らしく生きられる社会を目指すプロジェクト「My Health, Myself ― 私の健康のために、私ができること。」の一環として開催されたもの。
将来、医療従事者を志す高校生に向けてヘルスリテラシーの考え方を伝え、様々な体験機会を提供することで、参加者自身がヘルスリテラシーに向き合い、今後の医療との関わりについて考えて貰うことを目的としている。
シンポジウムの基調講演では、清水英治氏(ジョンソン・エンド・ジョンソン メドテック チーフ・メディカル・オフィサー)が、同社の取り組みと人生100年時代におけるヘルスリテラシーの重要性について講演した。講演は、「ジョンソン・エンド・ジョンソン メドテックの目指すこと」と「適切な医療にアクセスするための“力”:人生100年時代のヘルスリテラシー」の大きく2つのテーマで構成。
前者では、超高齢社会を迎える日本において、がん、心疾患、脳卒中などの主要疾患や、整形疾患、循環器疾患による要介護の課題が顕在化していることを説明。同社が外科全般、循環器、脳血管、整形外科の各領域で、テクノロジーを活用した精密治療や低侵襲手術を可能にする医療機器(メドテック)を提供することで、これらの課題解決に貢献していることを紹介した。
後者では、同社が「My Health, Myself」プロジェクトの一環で実施した国際調査の結果、日本のヘルスリテラシー自己評価が諸外国と比較して最も低いことを提示した。さらに、医療情報の判断基準がわからない人が多く、体調不良時も「様子を見る」傾向が強いなど、主体的な医療行動が少ないと指摘した。
その上で、「ヘルスリテラシーが低いと、健康増進行動の制約、治療参加姿勢の低下、入院率の増加などの悪影響があり得る」と説明し、患者が主体的に医療に関わることの重要性を強調。
清水氏は、講演の最後に、「少子高齢化は日本だけでなく世界が注目するチャレンジであり、皆さんがこの課題に取り組み、人々が健康でいられる豊かな社会を作ることができれば、それは大きな“チャンス”になる。医療の分野で皆さんがその役割を果たしてくれることを強く願っている」と次世代医療人材への期待を込めたメッセージを送った。
講演を通じて、参加者は超高齢社会における医療課題とその解決に向けたメドテックの役割、そして自らが主体的に医療に関わることの重要性について理解を深めた。

続いて、医療従事者を志す高校生のための実践的な医療機器操作体験を実施。医療従事者向けトレーニング施設である「ジョンソン・エンド・ジョンソン インスティテュート 東京」の最新設備を使用し、実際の医療現場で使われている機器に直接触れる貴重な機会となった。手技体験内容は、腹腔鏡鉗子操作、自動縫合器操作、心臓用カテーテル操作、人工膝関節手術支援ロボット操作の4項目。
その中で、腹腔鏡手術のシミュレーターでは、手元を見ずにモニター画面だけを見ながら細かい操作を行うという、通常とは異なる感覚に参加者は最初戸惑いを見せていたが、次第にコツを掴む様子が見られた。
心臓用カテーテル手技体験では、不整脈患者を想定し、3Dマッピングで映し出された心臓を見ながら、カテーテルを目的の場所まで到達させるという高度な技術を体験した。
指導にあたったジョンソン・エンド・ジョンソン メドテックの社員は、「医療技術の進歩によって、患者さんの体への負担を少なくできる低侵襲手術が可能になった。だが、経験豊富な医師であっても先端的医療機器を使いこなし実際の手術で使えるようになるには医療機器の安全・適正使用のためのトレーニングが必要である」と説明。
その上で、「とても繊細かつ熟練した技術が必要だということをわかっていただけたのではないかと思う」とコメントし、日本の医療の高度さと医師に求められる技術レベルの高さを感じてもらえるセッションとなった。

最後に、「My Health, Myself – 想いをかたちに」をテーマに、参加者一人ひとりが個人ワークに取り組んだ。具体的には、専用ワークシートを使用し、①あなたが思う「ヘルスリテラシーの重要性」を一言で表すと?、②どんな医療従事者になりたい?、③未来の医療に必要なことってなんだろう?ーの3つのテーマについて自分の考えを言語化・可視化した。
参加者たちは熱心にワークシートに向き合い、それぞれの想いを具体的に表現した。ワークシート記載後は2つのグループに分かれ、一人約1分ずつのアウトプット発表、臨床医経験のあるジョンソン・エンド・ジョンソン メドテック社員がフィードバックを行った。
その後、各グループから選出された代表者4名が全参加者の前で発表。「ヘルスリテラシーが向上すれば人の負担は減ると思う」、「患者さんの意思を尊重し、寄り添える医師になりたい」、「AIやロボットなどの科学技術をうまく活用しコントロールする力が必要」など、高校生らしい率直で多様な意見が発表された。
出浦伊万里氏(ジョンソン・エンド・ジョンソン メドテック メディカル・アフェアーズ ディレクター)は、「皆さんの多様で素晴らしいアウトプットに刺激を受した。将来、医療従事者として働かれるようになったとき、ともに未来の医療に貢献できる日を楽しみにしている」とのメッセージを送り、同シンポジウムを締めくくった。