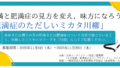塩野義製薬は5日、同社が共同研究機関として参画し徳洲会グループが実施した新型コロナ感染症(COVID-19)患者を対象とする市販後大規模臨床研究(ANCHOR試験)の新たな臨床データを公表した。
試験結果では、経口抗ウイルス薬を投与しない場合、COVID-19の罹患後症状(いわゆる後遺症、Long COVID)の発現率は約26%で、経口抗ウイルス薬の投与は、投与しない場合と比較して、COVID-19罹患後症状の発現リスクを統計学的に有意に14%低減した。これらの研究結果は、経口抗ウイルス薬がCOVID-19罹患後症状の抑制に寄与する可能性を示唆している。
主要評価項目(罹患後症状を有する患者の割合)結果は本年9月17~20日にシンガポールで開催された8th ISRV-AVG Meeting and 3rd IMRPで、副次評価項目(28日以内のCOVID-19関連の再受診頻度)結果は2025年11月2~4日にタイで開催されたAPCCMI 2025で報告された。
罹患後症状は、WHOにより「新型コロナウイルスに感染した人にみられ、少なくとも2ヵ月以上続き、他の病気による症状としては説明がつかないもの。通常は発症から3ヵ月経った時点にもみられる」と定義されている。
主な症状には、疲れやすさ・だるさ・咳・息苦しさ・味覚嗅覚障害・集中力の低下・ブレインフォグ(頭の中に霧がかかったような状態)を始め、様々な症状がある。この問題は日本のみならずグローバルで重大な課題であるが、抗ウイルス薬による罹患後症状の予防に関するエビデンスは限定的であった。
そこで徳洲会グループと塩野義製薬は、COVID-19と診断された外来患者を対象に大規模臨床研究を実施し、抗ウイルス薬の投与が罹患後症状の発現に与える影響を評価した。
同臨床研究は、日本の徳洲会グループ51病院でCOVID-19と診断された12歳以上の外来患者対象に実施した、多施設共同の前向き観察研究である。塩野義製薬は、共同研究機関として同臨床研究に参画した。
今回発表した臨床研究については、2024年2月1日から10月 31日までに登録された約9000例を対象とした。同臨床研究の主要評価項目である「罹患後症状を有する患者の割合」は、研究登録後28日目から84日目にかけて持続した、同一の症状(疲労、息切れまたは呼吸困難、咳、嗅覚障害、味覚障害)が少なくとも1つ確認された際に罹患後症状発現と定義し、罹患後症状の発現率を評価した。
抗ウイルス薬群(2181例:ゾコーバ、パキロビッド/リトナビル、ラゲブリオの併合群)と抗ウイルス薬非処方群(5518例)を比較した結果、罹患後症状発現率は抗ウイルス薬非処方群で約26%、抗ウイルス薬群で約24%であった。
抗ウイルス薬の投与により、発現リスクは統計学的に有意に約14%低減した(調整リスク比、0.86 [95%信頼区間、0.78-0.93]; P<0.001)。
ゾコーバについて単剤の効果を評価したところ、抗ウイルス薬非処方群と比較して発現リスクが有意に約14%低減した(調整リスク比、0.86 [95%信頼区間、0.79-0.95]; P=0.002)。
副次評価項目である「28日以内のCOVID-19関連の再受診頻度」については、抗ウイルス薬群は抗ウイルス薬非処方群と比較して、有意なリスク低減は認められなかった(調整リスク比、0.93 [95%信頼区間、0.83-1.04]; P=0.266)。
ゾコーバについての単剤評価では、抗ウイルス薬非処方群と比較してCOVID-19関連再受診リスクが有意に約12%減少した(調整リスク比、0.88 [95%信頼区間、0.78-0.99]; P=0.030)。
これらの結果から、抗ウイルス薬が急性期の症状改善および罹患後症状の発現を抑制する可能性や、再受診頻度を低減する可能性が示唆された。
2025年10月17日に公開された「5学会による新型コロナウイルス感染症診療の指針」では、“感染症、特にウイルス感染症における診療の基本は早期診断・早期治療であり、それが、個人にあっては、重症化予防、症状の軽減、早期の社会復帰に繋がる可能性があり、社会にあっても、蔓延の防止、入院する患者を減らすなどの負担の軽減につながる可能性がある“ことが言及されている。
徳洲会グループと塩野義製薬は、こうした指針で示された診療の基本を踏まえ、今後も協力してCOVID-19に関するエビデンスの蓄積と臨床現場への還元を推進していく。
◆同臨床研究研究代表医師の日比野真氏(湘南大磯病院 副院長/徳洲会呼吸器部会部会長)のコメント
罹患後症状への対処は、依然として大きなアンメットメディカルニーズの一つである。そのような中で、ANCHOR試験の今回発表した内容において、急性期における抗ウイルス薬の投与が罹患後症状の発現を抑制に寄与する可能性が示唆されたことを大変嬉しく思う。本研究は、COVID-19治療の新たな方向性を示す重要な成果であり、今後の臨床現場での治療選択や長期的な健康影響への対応に貢献することが期待される。