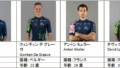後列左から、堀井 貴史、井上 浩輔、中山 富雄、鶴田 真也、石見 拓、室 繁郎、石崎 達郎(肩書/敬称略)
アストラゼネカは16日、大阪・関西万博(英国パビリオン)において、保健医療システムの変革を通じた「呼吸器疾病への包括的な挑戦」をテーマに『肺の健康への変革:日本とアジアへの機会』フォーラムを開催した。
同フォーラムでは、国内外の肺がん検診における最新の取組みや、肺がん検診と慢性閉塞性肺疾患(Chronic Obstructive Pulmonary Disease、以下、COPD)を含む肺疾患の早期発見にむけた包括的な医療体制の構築、エビデンスに基づいた検診の拡充等、様々な視点から、肺の健康に向けた活動に関するディスカッションを繰り広げた。
国内外の肺がん検診における最新の取組みや、肺がん検診と慢性閉塞性肺疾患(COPD)を含む肺疾患の早期発見にむけた包括的な医療体制の構築、エビデンスに基づいた検診の拡充等、様々な視点から、肺の健康に向けた活動に関する議論を展開。その後、社会的な負担となっている肺疾患を正しく早期に診断し、適切な治療へ結び付ける重要性は高まっており、包括的な肺の健康への道筋を見出すため、①肺疾患の包括的な早期診断、②学術的連携および関連エビデンスの創出、③ 教育機会の整備と人材育成・確保ーの共同宣言を行った。
同宣言は、包括的な肺の健康に対して関係者が継続的に協力し、この取り組みを通じて一人一人の健康寿命延伸と肺疾患による社会的負担軽減を目指している。
肺疾患には、肺がん、COPD、喘息等の非感染性疾患(NCDs)に加え、COVID-19などの感染症も含まれ、いずれも世界の死因の主要な部分を占めている。中でも、肺がんやCOPDはすべての死因において上位を占めているため、肺の健康は世界的な課題となっており、健康寿命の延伸に向けて、これらの早期発見・早期治療がますます重要になっている。
超高齢社会の日本においても、毎年12万人以上が肺がんと診断されており、肺がんは日本人のがん死亡原因第1位となっている。
また、COPDがあると肺がんのリスクを高めることが知られており、肺がんはCOPD患者の主な死因の1つだ。加えて、COPDは心不全等の心血管系疾患のリスクを高めることもわかっている。

フォーラムでは、海外や国内における産官学の有識者とともに、肺の健康に関するトランスフォームケア(保健医療の変革)に関する取り組みについて、現在の課題とその解決策について議論を展開した。
2025年5月に開催された世界保健総会(WHA)では、日本も共同提案国となった「包括的な肺の健康へのアプローチを推進・優先するための決議」が採択された。これを受け、肺の健康への対応では、保健医療システムの強化と医療へのアクセス拡大に加え、大気汚染、たばこの使用、職業上のリスクといった社会的決定要因への対策も不可欠であり、さらに多様なステークホルダーとの連携や部門横断的な協力の推進が求められることが強調された。
2025年9月25日には第4回国連NCDsハイレベル会合が開催される予定で、フォーラムでは「肺の健康を含むNCDs対策の機運の高まりを機会として捉えていくべき」と指摘された。
加えて、日本、オーストラリア、タイ、マレーシア等における肺がん検診の取り組みがベストプラクティスとしてリスクグループに応じた異なる肺がん検診のアプローチやAIなどの最新技術の活用なども紹介。「こうした優れた事例や革新的なモデル、実証的エビデンスの各国間での積極的な共有が、肺の健康に関する保健医療システムの変革につながる」との見通しが強調された。
続いて行われたパネルディスカッションでは、肺がんの検診や診断機会の最適化に向け、必要とされる戦略や連携のあり方について活発な議論が交わされた。
日本における肺がん検診に対する政策と、エビデンスに基づく政策立案(Evidence Based Policy Making、EBPM)を中心に、議論が展開された。
日本の呼吸器疾患対策は1951年の結核予防法に始まり、肺がん検診等の制度整備を経て発展してきた。だが、現在は、疾患ごとに異なる法制度(がん対策、感染症法、難病対策等)が分立しており、さらに自治体・医療機関・職域で検診データが分断されるため、包括的な管理・対応が困難となり、保険者ごとの検診・精密検査の運用差も大きくなっていることが指摘された。
厚労省が医療DX推進本部を設立し、全国的な健診・パーソルヘルスレコード・がん登録等のプラットフォーム構築を進行する中、各自治体や保険者間でもデータ連携を強化し、EBPM支援のためのデータ標準化が進行している。このような状況を受け、制度横断的な整備・一元化も見据えた政策発展や、技術革新・データ・制度の三位一体で「健康寿命延伸」「公平な医療アクセス」を推進することの必要性についても話し合われた。
日本における先進的な取り組みの事例として、奈良県広陵町と京都府京都市の事例が紹介された。広陵町においては、LDCTを契機としたCOPD疑い症例の発見から、診断・治療介入への「地域一体型」モデルが展開されており、住民の健康寿命延伸と医療費抑制の両立を目指している。
また、京都市では、独自の統合データベース(国保・後期高齢・がん登録等を匿名連結)を活用し、肺がんと慢性肺疾患の診療実態と予後分析を通じた政策提言が行われており、都市型EBPMモデルとして注目されている。
肺の健康は世界的な課題であり、2021年には肺疾患が1800万人以上の死亡原因となっている。そのうち非感染性疾患、特に肺がんはがん死の中でも男女ともに最多であり、またCOPDも死因の4位であるなど、世界の死因の主要な部分を占めている。こうした状況から、2025年5月に開催された世界保健総会では包括的な肺の健康に対する決議が採択された。
日本においても世界同様、肺がんはがん死の1位を占めており、2024年には男女計で約7万8000人が肺がんにより命を失っている。また、COPDは実際に治療を受けている患者数が約38万人にとどまる一方で、潜在患者数は500万人以上と推定されている。
未診断COPDは心疾患や肺がんなど他の疾患に合併しているケースもあり、それぞれの疾患への治療介入を困難とするなど医療にも社会にも大きな負荷を与えていると想定されている。

こうした背景から、肺疾患を正しく早期に診断し、適切な治療へ結び付ける重要性は高まっており、包括的な肺の健康への道筋を見出す必要性について、①肺疾患の包括的な早期診断、②学術的連携および関連エビデンスの創出、③ 教育機会の整備と人材育成・確保ーの共同宣言が行われた。
肺疾患の包括的な早期診断の推進は、地方自治体・地域医師会など関連するステークホルダー間の議論の活発化および、新たな技術の導入も考慮した肺がん検診および他の呼吸器疾患の早期診断体制の充実を図るもの。
学術的連携および関連エビデンスの創出では、アカデミア・行政などの間での、エビデンス・ガイドライン・政策など、関連情報の積極的共有および、疫学・実臨床・費用対効果などの必要なエビデンス創出を活発化する。
教育機会の整備と人材育成・確保では、画像読影やスパイロメトリー実施、また関連する新たなテクノロジーの導入に必要な能力の同定および教育機会の整備や人材確保への協働を推進する。