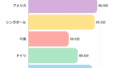配置薬の歴史(1)
日本古来の薬法を守るため
平城天皇の大同三年(808年)に勅撰書として編纂された「大同類聚方」がある。これは平城天皇が、我が国古来の薬法が、仏教と共に伝来した漢方の隆盛によって、衰微しそうになっているのを心配され、安部真直、出雲広貞らに命じて、日本古来の薬の良いところを復興させるのを目的に、日本の銘薬を記載させたもので、前百巻で構成されている。□□第一巻から第十三巻までは用薬部で、薬名は、植物では、山草、原野草、木、穀類など279種、鉱物36種、生物79種があげられている。
第十四巻から第百巻までが処方部で、百数十の病名が記載され、症状によって処方があげられ、太古から民間で創薬され、秘伝として、それまで数百年も経過したものや、新しく新羅、百済、高句麗等からもたらされた処方も記載されている。中には仏教と共に伝えられた漢方を取り入れた処方のものが多く見られる。□□例えば、日本特有の原料薬としては、「センブリ(当薬)」があり、中国には無い植物であり、そのため漢方には出てこない。しかし、「大同類聚方」にはセンブリが処々に記載されている。センブリが古代から日本の民間薬として非常に効果をあらわしていたことの証である。竜胆(リンドウ)等の苦味健胃、消化、整腸薬の代わりに処方に用いられたことも考えられる。
民衆の健康を支えた「持ち薬」 古代から、豪族やその氏神神社は、一族の健康と領地領民を守るための医薬を大切にし、良い医薬品を求め、これを一族の「持ち薬」として領民に分け与え、部族全員が健康で強力になることで、一族の発展拡大を図った。また、仏教が漢方医学の知識や薬を伴って伝来するや、民衆の信仰を集めるため、心の迷いは仏教の教義をもって救い、病気等は、新たな伝来した漢方医学の知識による対策と薬を施すことで、領民等を救った。東大寺が救命丸、西大寺が豊心丹というように有名な寺院のほとんどが薬を作り施薬していた。現在もその痕跡を見ることができる奈良県葛城市の当麻寺は役行者由来の寺として、陀羅尼助を販売する御坊がある。□□施薬としては、推古天皇の十九年(611年)の五月五日、推古天皇は百官を従えて、大和の国宇陀郡に薬草採集され、延喜式には多数の薬種が大和より献上されたとある。仏教伝来後、隋・唐との交流がはじまり医学、薬物が伝えられ、唐の制度に習って医薬の制度が作られた。大和の多くの神社、仏閣から施薬がほどこされ、大峰の薬草が後代京都の公卿に珍重されなど、大和の諸寺神社の薬は注目され、また、修験者等が全国各地に持ち回り広める役を持った。そして時間の経過とともに中世の頃には寺院神社の門前の民間人も製薬をするようになる。室町時代大永五年(1525年)姫路の広峰大明神の神主井口太夫の知遇を得て、黒田孝高(如水)の祖父黒田重隆は黒田家伝の目薬処方「玲珠膏」(れいしゅこう)を売り出し、大儲けをし、金貸し業を経て備前福岡の有力豪族となり、御着城主小寺政職に仕官することができた。1455年に著された中原康富の「康富記」に1453年5月2日(6月17日)の条に「諸薬商買の千駄匱申し間事談合とするなり。薬売るもの施薬院相計る所なり。」と書いてあり、また、「御府文書」には1460年に京都の四府賀興丁座の中に薬品類を商いする商人がいたことが記されている。全国に薬の行商は広まり、ただ売り歩くだけでなく、それぞれの地区の拠点になる寺、神社、家に卸し若しくは委託販売または施薬に多種多様な業者が持ち歩き、売り込み吹聴する機会も増えていった。
配置薬の歴史(2)
きっかけは江戸城腹痛事件
1690年に江戸城内において腹痛をおこした三春城主の秋田輝季に富山藩主前田正甫が合薬富山反魂丹(はんごんたん)を服用させたところ、秋田輝季の腹痛が驚異的に回復した江戸城腹痛事件という逸話がある。このことに驚いた諸国の大名が富山売薬の行商を懇請したことで富山の売薬が有名になり、また「先用後利」を基本とする現代の医薬品配置販売業の基礎を作ることになった。安静7年(1860年)2月「国中組合取極連印帳」という仲間規約をつくり、幕府の方針に沿った業態にするため「南都薬種取締所」の指導のもとに商売秩序の維持発展のために、米田丈助を筆頭とした77名の業者で作り上げた。また慶応2年(1866)7月、72名の大和の業者は、越中国富山の総代3名、加賀領総代2名との間で、話し合いって15ヶ条におよぶ議定取締書を作成した。
全国への発展「組合取極連印帳」の要点(13項目)
一、 公儀の言われることを守り、南都薬種取締所の規定に反しないこと。
一、 薬の原料売買は値段を守って規定どおりとし、不正な売買はしないこと。
一、 斤目が不同のものが多いので京大阪の定法どおりに調整し、一斤は二百匁とすること。
一、 人参その他にニセものが多くなった、人命にもかかわるので、見つけたら年行司惣代に届け出ること。
一、 他国の医家へ薬種を売り込んではならない、又他国から来て医家その他へ売ってはならない。
一、 薬種株や合薬株にて産地で直接買い入れ、他国へ出荷などしないこと。
一、 組合仲間以外の者などを使って和薬種を買い集めさせないこと。
一、 合薬仲間は薬のほか染料、絵能具、香具、砂糖を売って商売しているが、そのため仲間の差支えにならぬこと。
一、 合薬仲間は、同じ銘柄や紛らわしい薬を差控え、他の薬を誹謗したり、値下げ競争をしないこと。
一、 奉公をやめた者、年季をすませた者は、先主と話合ってから傭うこと。奉公人が心得ちがいで持ち出した品物とわかったら、その主人にしらせること。
一、 薬種札を譲り受けたら、行司に届け出て、仲間振舞料二両を年行司に出すこと。
一、 薬種の売掛代銀不払いの向きあると、仲間へ知らせ、勘定がすむまで互に商売を差し控えること。
一、 年行司の費用として薬種屋は銀五分、和漢屋、合薬屋は二分五厘をだすこと。
右の條條一同で取極めた以上は、必ず守り、取引し、不作法の者は取締所へ申し出て、仲間から除名されても異議を申し立てず、一同で協定書に連印した。
安政7年2月
葛上郡今住村大和と富山の業者の議定書「議定取締書」(14項目)
一、 近年薬種、紙、米、運送、宿料など高くなったので、薬も三割値上げすること。
一、 不正薬種、毒になる薬は決して扱わぬこと。
一、 同じ銘柄の薬でも文字や筆法をかえ、紛らわしくしないこと。
一、 薬は人間の病苦を救うものだから、大切に調合すること。
一、 値引き、誹謗を謹む。もし心得違いの者あれば確証をつけて申し出ること。
一、 得意先へあとから行き、値引きして売り込むことは絶対にしないこと。
一、 重ね置きになったとき、他人の薬をけなし、自分の薬を自慢してはならない。
一、 やめた奉公人、暇を出された奉公人は、先主にことわってから使うこと。
一、 奉公人の賃銀は、一か年につき上級で銀五百匁、中級で三百五十匁、下級で二百匁と定めること。
一、 他人の空の薬袋を引きあげ、自分名の薬袋を入れるようなことは決してしないこと。
一、 旅先で酒色におぼれ、博打をする者を見つけたら、意見し、聞き入れぬ者は帳面荷物を取り上げ国元へ送ること。
一、 宿で急死、急病などがあると、近くで見聞きした者は馳せつけ、世話をすること。
一、 定宿では、原則として同部屋のこと。
一、 右の仲間規定をした上は一年に一回は参会する、不参加の者も一様に費用を負担すべきだ。他国へ出て、心得違いして一か条でも約束違反があれば、取締所へつき出し、取締ること、右の費用は不法人から弁済される。
仲間一同取締議定書をつくり、連印した。
慶應2年7月29日
以下七十七名の署名捺印
大和の署名捺印者72名は、全員が国(藩)外で配置売薬に従っていた業者である。富山、加賀領(越中国の加賀藩領のこと)の5人は、いずれも越中売薬の代表であって、協議のためわざわざ呼び寄せたもの。
このように江戸時代末までには富山、奈良、滋賀、佐賀、岡山の売薬もかなり業として整備され全国的に広がりを持つ業に発展していた。
配置薬の歴史(3)
先用後利 売薬から発生した概念である「先用後利」という言葉とそれに拠って成り立つサービスシステムである医薬品配置販売業、そのもとである「先用後利」とは、「用いることを先にし、利益は後から」とした富山売薬業の基本理念である。江戸元禄期の創業時代より現在まで脈々と受け継がれてきた。富山藩二代目藩主前田正甫公の売薬に対する訓示「用を先にし利を後にし、医療の仁恵に浴びせざる寒村僻地にまで広く救療の志を貫通せよ。」と伝えられる。これは、創業当時既に全国に広まっている売薬の市場に新たに藩の事業として市場に入り込むには、他の既存の売薬と同一視されない新たな販売戦略を持たなければならなかった。□□当時はおよそ200年にわたる戦国の騒乱も終わり江戸幕府および全国の諸藩においては救国済民に努め、特に領民の健康保持に力をいれた。しかし、疫病は度々起こり、医薬品は不十分な状態であった。医薬品販売も室町時代から続く売薬はあっても、店売りは少なく、薬を取り扱う商人の多くは誇大な効能を触れ回る大道商人が多くいた。また、地方の一般庶民の日常生活では貨幣の流通が十分ではなかったようで、貨幣の蓄積が少ない庶民にとって医薬品は家庭に常備することは希であり、必要に応じて商人等から購入せざるをえなかった。□□この様な社会背景の中、医薬品を前もって庶民の手近に預けておき、必要に応じて使ってもらう、そして薬の代金は後日支払ってもらう「先用後利」の方法は、画期的サービスシステムとして時代の背景に合い、要望を引き起こした。□□当初はそれぞれの地域地区の纏め役世話役の家、寺等に預け、次第に一般の家庭に預けるようになっていたようである。江戸時代における配置販売業者はただ薬だけを扱うのではなく、訪問先の産物を他の地域に、また他の地域の産物を訪問先の地域に紹介する。また産物だけでなくいろいろな地域の様子や情報を提供することを主な業にしたようであり、例として富山の売薬業者が薩摩藩へ入国を許され、その経緯などがよい例なると思われる。当時の売薬業者は、現代の総合商社のような業をする大規模な業者も存在したのである。
薬事法制定
明治に入り西洋の医学(西洋医学)が主流になり、今まで永年にわたり我国で育った漢方医学は国の政策として否定廃止され売薬業も非常な苦境に立たされた。1886年頃輸出売薬を開始し、明治の末から大正にかけて輸出売薬は大きく伸び、中国・アメリカ・インドなど数多くの国と交流があった。大正の初めがピークに達し、日貨排斥運動が活発だった中国市場の8割が輸出売薬で占められていた。□□この動きによって薬種商は、大規模な製薬メーカーへ、また西洋医学に合った医薬品を製造し、医者や販売業者に卸す業者、店舗を構えて庶民に販売する業者へ行商形態からの移行が大きく起こった。20世紀に入ると売薬に関する制度や法律が次々と整備され、1914年に売薬の調整・販売ができる者の資格・責任を定めた「売薬法」が施行、1943年品質向上確保のため医薬品製造はすべて許可制とする「薬事法」となった。
参考資料:
滋賀のあゆみが分かる歴史年表
薬の歴史と配置薬の沿革(薬の年表)
薬の歴史 | 樋屋製薬株式会社・樋屋奇応丸株式会社 樋屋製薬 https://hiyakiogan.co.jp › content › fukuyo › history
「配置薬、歴史」での検索、AI による概要および配置薬の歴史の詳細について
配置薬の由来 株式会社富士薬品 https://www.fujiyakuhin.co.jp › home_medicine › history
配置薬の歴史 一般社団法人東京都医薬品配置協会 http://www.okigusuri.or.jp › rekisi
配置薬の歴史(3) ashitaka-yakuhin.co.jp https://www.ashitaka-yakuhin.co.jp › three