第2回再生医療抗加齢学会(大会長:大慈弥裕之福岡大学名誉教授)が19日、「抗加齢・美容医療における再生医療・幹細胞医療の実際と課題」をテーマに大阪市内で開催された。同学会では、抗加齢・美容医療において先進的な医療を実践している医療機関からの発表が相次ぎ、安全性・有効性に関する臨床評価および課題についてディスカッションを展開。「未だ個々の治療での検証も明らかでないまま再生医療を用いた美容医療が進められている現状」が指摘され、「美容医療における倫理性を持った医療人育成の重要性」が確認された。
再生医療は、様々な医療領域において我々の健康や生活の質向上に大きく貢献する可能性を秘めている。抗加齢医療や美容医療においても、安心・安全をバックグラウンドに受療者のアンチエイジングや整容の改善に寄与しており、一般市民からの期待度も大きい。その一方で「施術者は基礎的検討が十分なされていない新規治療や未承認医療を医師の裁量でしばしば施術している」という課題がある。一部に合併症も報告されているのが現状だ。
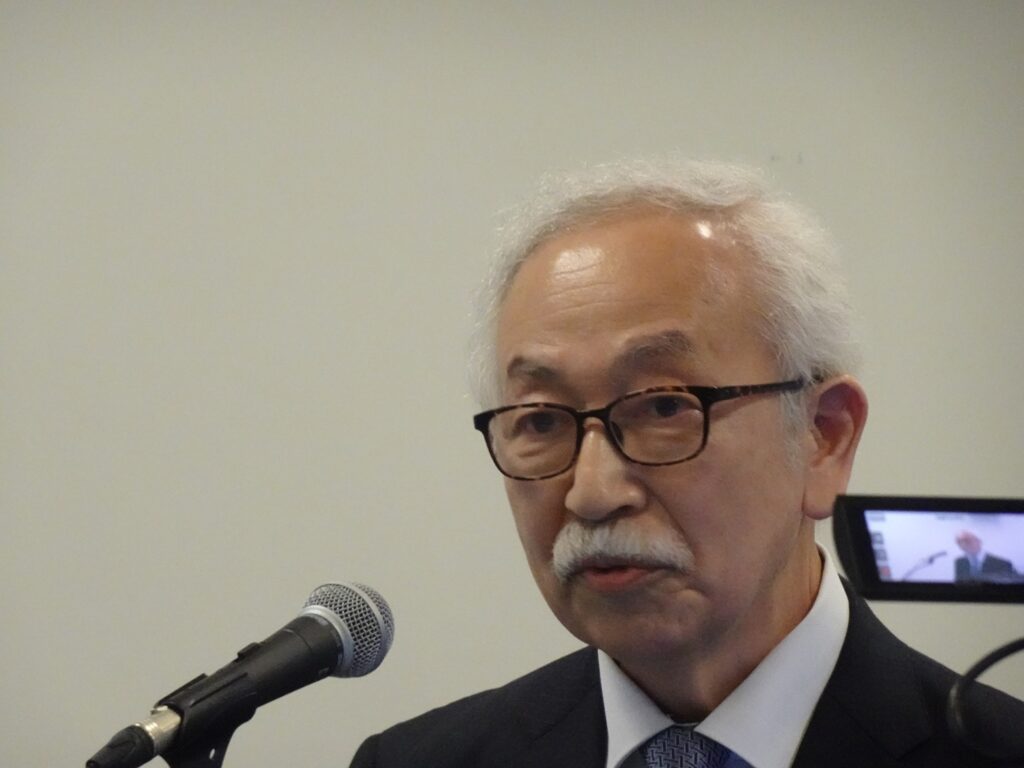
「抗加齢・美容医療における再生医療の実際と課題」をテーマに講演した楠本健司氏(くすもと形成外科クリニック院長、関西医科大学名誉教授)は、まず、「現在、再生医療の中で、一定の細胞医療に対して再生医療等安全性確保法(再生医療法)で届け出義務が付けられているが、その半数以上の提供計画は多血小板血漿で療法(PRP療法)が占めている」ことを紹介した。
PRP療法は、自己の静脈血を遠心分離して得た濃縮した血小板から内包する細胞増殖因子を多種・多量に放出させ、目的とする細胞や組織の活性化、組織再生に適用するもの。抗加齢医療や美容医療の領域では、シワやたるみ、美肌治療、薄毛治療などで使用されている。
楠本氏は、適用外使用である塩基性繊維芽細胞増殖因子(bFGF)を添加したPRPの投与にも言及し、「発赤、浮腫、熱感、痛み、圧痛、皮膚出血、表皮ピーリング等の一過性の合併症が出現する症例がある。皮膚の発赤は数日、皮下出血などは色調が消退するまで1~2週間を要する」と報告した。
さらに、「再生医療は、医療や難病治療から抗加齢医療、美容医療に至るまで広い領域で期待されており、自由診療の再生医療を再生医療法の枠に入れた点で画期的である」と指摘。
他方で、「この法体系の中で再生医療が多種・多様で多量等であるため判断や審査、有害事象の報告が適切に行われていない」課題も挙げた。
また、「再生医療法の枠外で組織再生を促すと考えられる幹細胞上静やエクソソームなどの新規の再生医療が、個々の治療での検証も明らかでないまま進められている」現状を懸念した。国内でエクソソーム投与の可能性がある市中医療機関件数は188件に上り、「エクソソームの静脈内投与による死亡例の情報」も流れている。
楠本氏はこうした現況を踏まえて、「再生医療法における届け出義務はあくまでも“届け出”であって認可ではないことを認識する必要がある」と断言。その上で、「健全な抗加齢・美容医療・再生医療は、健全な医療フィールドで育つ」と訴えかけた。


