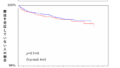絶滅危惧種保全研究の新展開に期待
国立環境研究所、岩手大学、猛禽類医学研究所、どうぶつたちの病院 沖縄、岐阜大学を中心とする研究グループは25日、独自に開発した手法を用いて、日本国内に生息する絶滅危惧種である、ヤンバルクイナ、ライチョウ、シマフクロウ、ニホンイヌワシからiPS細胞(人工多能性幹細胞)を樹立したとと発表した。同発表は、世界で初めて絶滅危惧鳥類からiPS細胞の樹立に成功(4種同時報告)したことを明らかにしたもの。これらのiPS細胞は、種ごとに細胞の品質(分化能力)が異なる。
絶滅危惧種を含めた野生動物では、生体を使った実験は困難だ。同研究で樹立したiPS細胞を神経様細胞などの細胞に分化させることで、病原体感染実験などの高度な感染症リスク評価への応用等が可能になる。同研究で樹立したiPS細胞の利用により、今後、絶滅危惧種保全研究の新展開が期待される。
なお、同研究成果は、24日にNature publishing groupが発行する『Communications Biology』に掲載された。
生物多様性のホットスポットである我が国には多数の絶滅危惧種が生息している。環境省レッドリスト2020では哺乳類34種、鳥類98種、爬虫類37種、両生類47種、魚類169種が絶滅危惧種として指定されている。
また、環境省による保護増殖事業では、ヤンバルクイナやライチョウ、シマフクロウ、ニホンイヌワシなど(脊椎の対象種は、哺乳類4種、鳥類16種、爬虫類1種、両生類1種、魚類5種)を対象種としている(図1)。
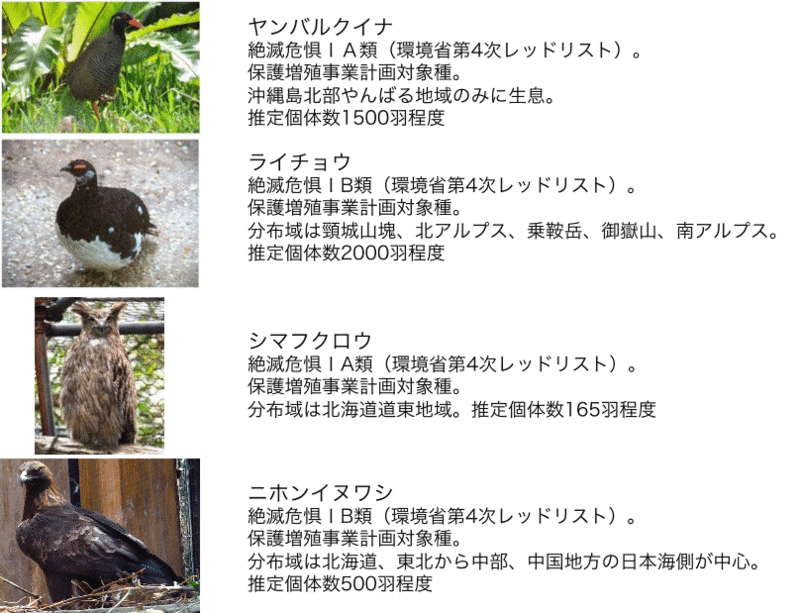
昨今、保全生物学において、生息域内保全と細胞の凍結保存も含めた生息域外保全を一体として進める統合型保全策「ワンプランアプローチ」が提唱され、国立研究開発法人国立環境研究所でもその研究が進められている。
国立環境研究所では、環境試料タイムカプセル棟において、域外保全の一環として絶滅危惧種を中心に、2002年から野生動物の体細胞等を長期保存用タンクの中で凍結保存している。
さらに、保存した体細胞を用いて、感染症の感受性評価や培養細胞から抽出したDNAを用いた野生動物のドラフトゲノムの解読も進めている。
野生動物から神経細胞や肝細胞が取得できれば、野生動物の感染症や汚染物質によるリスクを試験管内でより高度に評価することが可能になるが、現実的に取得できる体細胞は皮膚または筋肉由来の細胞が中心になる。
そこで、研究グループはiPS細胞技術に着目した。iPS細胞は皮膚や筋肉などの細胞から樹立可能だ。さらに、神経細胞や肝細胞を含めて、様々な細胞に分化できるため、試験管内での病原体感染実験や汚染物質ばく露試験によるリスク評価が可能になる(図2)。
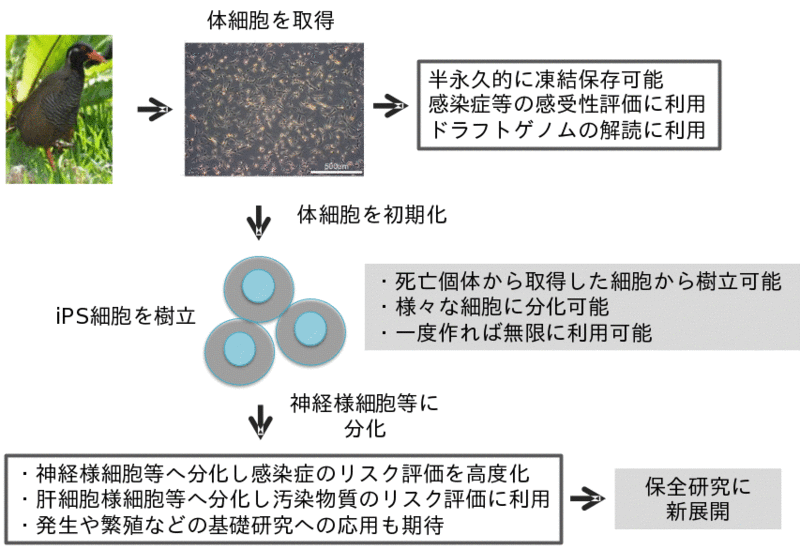
実際にヒトの研究では、皮膚等から採取した細胞を基にしたiPS細胞を、特定の細胞に分化させ、感染症研究や毒性評価に利用されている。また、受精卵の利用が難しい絶滅危惧種において、iPS細胞は試験管内における発生、生殖、繁殖等の基礎研究への利用も期待される。
このように絶滅危惧種研究においては、iPS細胞を用いることで様々な新規情報の取得が可能になり、保全研究における新展開が期待できる。国際的にも絶滅危惧種の保全研究においてiPS細胞などの多能性幹細胞の有用性は認識されており、米国サンディエゴ動物園を中心とするFrozen Zooプロジェクトや、欧州で進められているFrozen arkプロジェクトにおいて、既に絶滅危惧哺乳類の保全研究に利用されている。
一方で、絶滅危惧種の保全を考える上で重要な情報を提供する可能性があるiPS細胞技術の応用は鳥類ではあまり進んでおらず、絶滅危惧鳥類におけるiPS細胞の樹立は報告されていなかった。
そこで、同研究では絶滅危惧鳥類のiPS細胞の樹立方法を開発し、iPS細胞を樹立した。死亡個体から取得したヤンバルクイナ、ライチョウの体細胞と、新生羽軸から取得したシマフクロウ、ニホンイヌワシの体細胞を使用してiPS細胞の樹立を試みた。鳥類の羽は特定時期に生え変わる。新しく生えてきた羽の羽軸を新生羽軸と呼ぶ。生え変わり時期の新生羽軸は、治療や健康診断のための保定の際に、偶発的に落下することがある。この新生羽軸の一部から体細胞を取得した(図3)
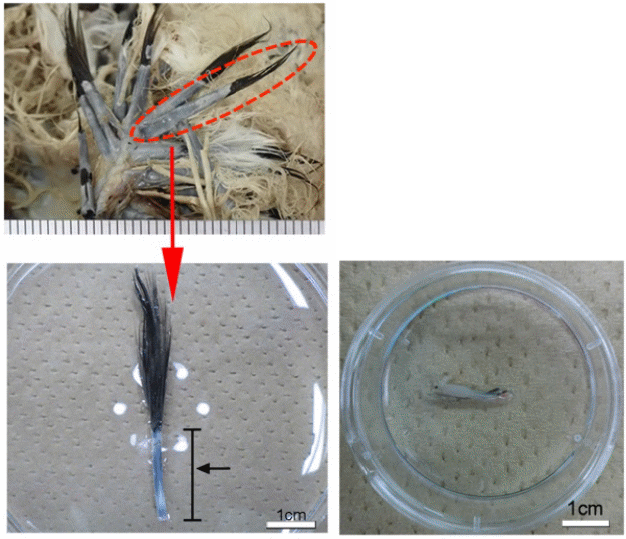
動物種ごとにiPS細胞の樹立に必要な遺伝子セットや培養条件が異なるため、マウスやヒトで使用されている方法をそのまま使用しても、鳥類のiPS細胞の樹立は困難である。研究グループでは、以前の報告で転写活性を高めたOct3/4を含めた6つの初期化遺伝子を使用することで効率的にニワトリのiPS細胞の樹立に成功している。
同研究では、この先行研究を発展させて、転写活性を強化したOct3/4を含めた7遺伝子をヤンバルクイナ、ライチョウ、シマフクロウの体細胞に同時に導入して、これらの野生鳥類のiPS細胞の樹立を試みた(図4)。
同研究で初期化したヤンバルクイナ、ライチョウ、シマフクロウの細胞は、マーカー染色等から未分化な状態を示した(図3)。
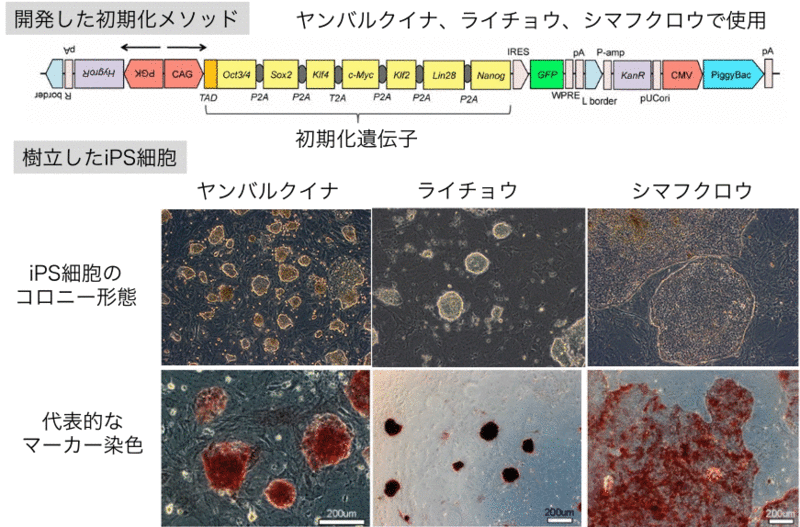
次に、より詳しい初期化した細胞の性質解析を進めた。遺伝子発現は、樹立した細胞の性質を明らかにする上で重要な解析である。国立環境研究所環境ゲノム科学研究推進事業では、ヤンバルクイナやライチョウなどのドラフトゲノム情報を取得・公開している。
同研究では、国立環境研究所で解読が進められたドラフトゲノムを利用し、初期化したヤンバルクイナ、ライチョウ、シマフクロウの細胞の遺伝子発現を解析した。
その結果、遺伝子発現解析を通じても、初期化した細胞が未分化な状態を示すことが明らかになった。加えて、試験管内、生体内の両方で三胚葉への分化が可能であったため、初期化した細胞は、iPS細胞であることが示された。また、これらのiPS細胞から神経様細胞への分化にも成功した。
樹立したiPS細胞の品質(分化能力)に関する情報は、細胞の分化を進める際に重要な情報になる。細胞の品質としては、iPS細胞やES細胞は、大きく分けて2つのタイプに分類されると考えられている。一つ目は、マウスを代表とするナイーブ型。もう一つはヒトを含めた多くの動物のプライム型だ。ナイーブ型の方が様々な細胞に分化できる能力が高く、プライム型幹細胞をナイーブ型に高品質化する取り組みが進められている。同研究では、ライチョウはナイーブ型に近い性質を示し、シマフクロウはプライム型に近い性質を示した。また、ヤンバルクイナはナイーブ型とプライム型の中間の性質を示した(図5)
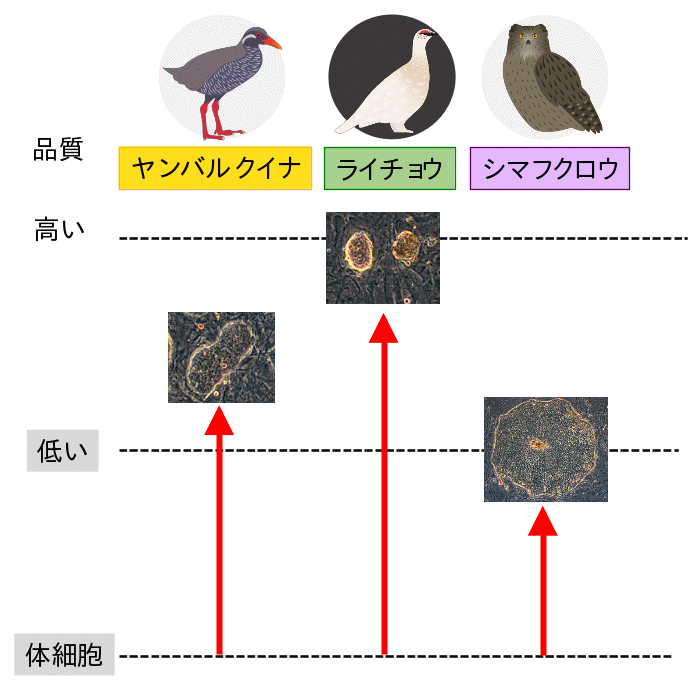
同研究では、同じ初期化方法を使用して樹立したにも関わらず、ヤンバルクイナ、ライチョウ、シマフクロウのiPS細胞は性質が異なることが明らかになった。
特に、ライチョウのiPS細胞は、分化能力が高いマウスiPS細胞(ナイーブ型)に近い性質を示したため、より多様な細胞に分化が可能である。
さらに、同研究では、ニホンイヌワシのiPS細胞の樹立も試みた。ニホンイヌワシのiPS細胞の樹立には、新たに遺伝子を追加して合計8遺伝子を使用した(図6)。
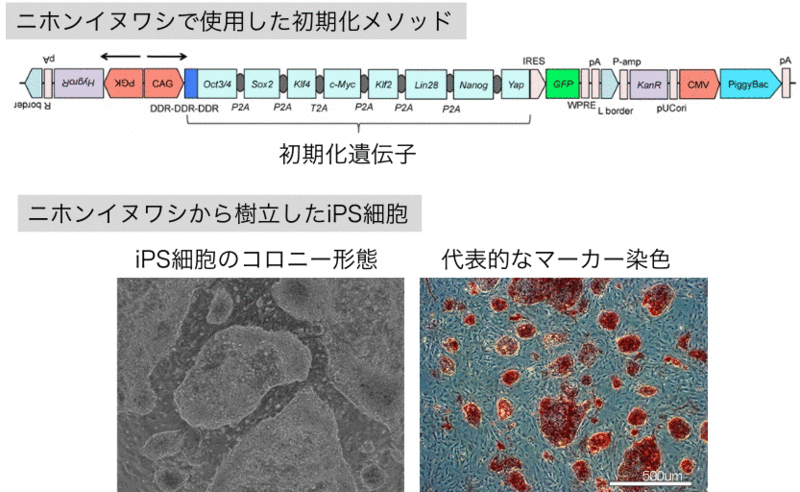
初期化した細胞は、未分化な状態を示し、試験管内、生体内の両方で三胚葉分化が可能であることが確認された。これらの結果から、初期化したニホンイヌワシの細胞は、iPS細胞であることが示された。
野生動物を大量死に導く要因の一つとして、感染症があげられる。特に、2004年以降断続的に国内の野鳥や家禽で発生している高病原性鳥インフルエンザは、絶滅危惧種の生息状況に影響を与える可能性がある。
高病原性鳥インフルエンザで死亡した多くの野生鳥類は、脳炎により死亡することが分かっている。同研究で樹立したヤンバルクイナ、ライチョウ、シマフクロウ、ニホンイヌワシのiPS細胞を、神経様細胞等に分化誘導すれば、これらの絶滅危惧鳥類の感染症によって発症する脳炎による死亡リスクの高度な評価が可能になる。
また、鉛中毒のような汚染物質による中毒も野生動物を大量死へ導く要因の一つとして知られている。国立環境研究所でも鉛による鳥類への影響の調査を進めているほか、鉛中毒を発症した鳥類は、神経症状を発症することも分かっており、野生鳥類の毒性評価においても神経毒性評価は重要であると認識されている。
同研究で樹立したiPS細胞を肝細胞様細胞や神経様細胞に分化し、ばく露実験に利用することで、汚染物質の代謝や神経毒性等の高度な評価が可能になる。
さらに、受精卵を使った研究が極めて難しい絶滅危惧鳥類において、同細胞を用いた試験管内での発生、生殖、繁殖等の基礎研究を通じて、効率的な繁殖を進めるための基礎知見の集積も期待される。
今回樹立したiPS細胞は、凍結保存することで半永久的に利用が可能であるため、環境試料タイムカプセル棟において保存している。なお、同研究は、日本学術振興会「科学研究費助成事業の研究助成を受けている。