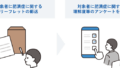住友ファーマは14日、開発中の再発または難治性急性白血病を対象としたメニン-KMT2Aタンパク質結合阻害剤「エンゾメニブ」について、P1/2試験の日本人のデータ解析においても良好な認容性が確認されたと発表した。エンゾメニブが、日本人の再発・難治性急性白血病患者において、全体集団と同様に良好な安全性プロファイルと臨床効果を示したもの。
エンゾメニブのフェーズ 1/2 試験の新たな予備的な臨床データは、米国血液学会(ASH)2024年年次総会(開催時期:2024 年 12 月、開催場所:米国)において発表されたが、10 月 10日~12日まで神戸市で開催されたJSH2025 では、それらのデータとともに日本人患者のデータを新たに抽出し、解析した結果を口頭発表された。
同試験の安全性解析対象集団(全体集団)は、急性白血病患者84例で、そのうち94%(79/84 例)が急性骨髄性白血病であった。試験には多様な患者が組み入れられ、白人以外が 47.6%(40/84例)であり、うち日本人は22例で、その 96%(21/22 例)が急性骨髄性白血病であった。
エンゾメニブは、40mg 1 日 2 回から 300mg 1 日 2 回までの用量を、28 日のサイクルで連続投与された。全体集団と日本人集団のいずれにおいても、エンゾメニブの忍容性は良好で、エンゾメニブと関連のある有害事象の発現率は全体的に低く、用量制限毒性(DLT)は認められなかった。
分化症候群は全体集団の 10.7%、および日本人集団の13.6%の患者で報告されたが、死亡例やエンゾメニブの投与中止に至るものは認められていない。
また、用量最適化コホートにおける200mg1日2回および300mg1日2回の投与量における予備的な有効性のデータも発表した。このデータには、KMT2A 遺伝子の再構成またはヌクレオホスミン1(NPM1)遺伝子の変異を有し、エンゾメニブを少なくとも1回投与され、メニン阻害剤の治療を受けたことのない全例のデータ(全体集団:40例、日本人集団:12例)が含まれている。
全体集団では、ELN-2017 ガイドラインに基づく客観的奏効率(ORR)は 62.5%(25/40 例)、完全寛解+部分的血液学的回復を伴う完全寛解(CR+CRh)達成率は 37.5%(15/40 例)であった。日本人集団における ORR は 75.0%(9/12例)、CR+CRh 達成率は 41.7%(5/12 例)であった。
これらの結果より、エンゾメニブは、日本人の再発・難治性急性白血病患者において、全体集団と同様に良好な安全性プロファイルと臨床効果を示し、KMT2A再構成または NPM1遺伝子変異を有する再発または難治性の急性白血病患者の治療に、エンゾメニブが重要な役割を果たす可能性が示唆された。
白血病は造血組織に発生する血液悪性腫瘍の一種で、骨髄における血液細胞(通常は白血球)の無秩序な増殖を特徴とする。白血病の一種である急性白血病では、血液細胞が急速に増殖し、突然症状が現れるため、早急な治療が必要とされている。急性骨髄性白血病患者の約30%がNPM1 遺伝子の変異を有し、5~10%が KMT2A 遺伝子の再構成を有しているといわれている。
骨髄線維症がん治療剤「ヌビセルチブ」P1/2試験も好結果
また、JSH2025では、再発または難治性の骨髄線維症患者を対象とした PIM1阻害剤「ヌビセルチブ」(開発コード:TP-3654)のフェーズ 1/2 試験に関する臨床データも発表された。こちらは2025年欧州血液学会(EHA、開催時期:2025年6月、イタリア ミラノ)で発表した内容で、ヌビセルチブの忍容性は良好で、症状の反応と相関するサイトカインおよび脾臓容積の改善を含む臨床効果が示唆された。
骨髄線維症は稀な血液悪性腫瘍の一種で、JAKシグナル伝達経路の調節異常によって骨髄に線維組織が蓄積することを特徴とし、血液細胞の産生に影響を及ぼす場合がある。骨髄線維症は重篤かつ希少な疾患であり、世界中で毎年10万人あたり0.7人が新たに発症している。