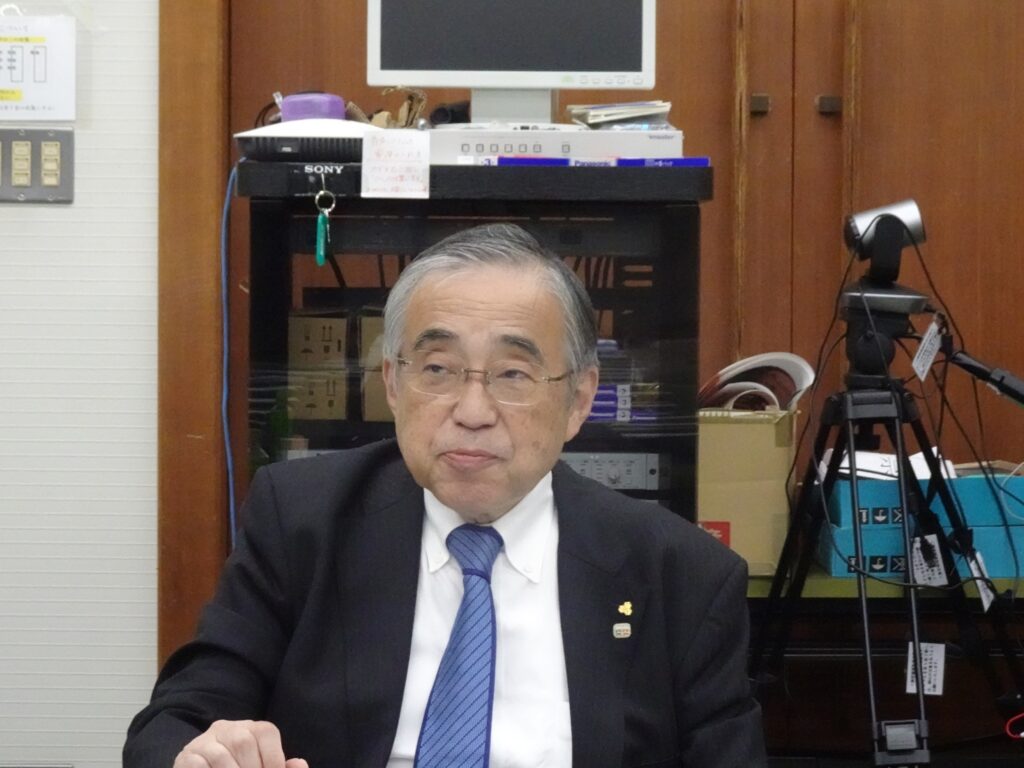
大阪府薬剤師会は1日、定例記者会見を開き、乾英夫会長が大阪府薬剤師会の薬剤師生涯研修認定制度が9月12日付けで薬剤師認定制度認証機構の認証を受けた(認証番号:G28)と報告。「長年の懸案であった大阪府薬薬剤師研修認定制度は、来春までを目処としているe-ラーニングなどのシステム化の準備ができ次第スタートする」と述べ、「この制度を通じてかかりつけ薬局・薬剤師がしっかりと活躍するための資質を構築していく。スタートするまでは、会員・非会員も含めてこの制度をしっかりと周知したい」と訴求した。
乾氏は、厚労省からの委託事業である2025年度地域医薬品提供体制構築推進事業にも言及し、「今後、大阪府薬の56支部それぞれに地域医薬品提供体制連絡協議会を設置して、地域の医師会、歯科医師会、訪問看護ステーション、行政等と連絡を取りながら、薬剤師がその地域に合致した形で医薬品提供できるように進めていく」考えを強調した。なお、薬局機能および夜間・休日体制については、各支部で12月中に薬局のリスト化を行い、来年1月に大阪府薬に報告するスケジュールになっている。
会見では、9月10日に開催された日本薬剤師会の「薬剤師組織のあり方等に関する特別委員会」についても、「会費の値上げ」、「日薬が会員を直接管理したい趣旨」等について話し合われたと報告。乾氏は「会費の値上げは慎重に対応する必要がある」と明言し、薬剤師組織のあり方についても「地域薬剤師会も含めて、こちらからも意見を述べて行きたい」と語った。

大阪府薬剤師会の薬剤師生涯研修認定制度は、大阪府薬独自の研修プログラムの構築を大きな特徴とする。伊藤憲一郎副会長は、「シラバスに沿ったかかりつけ薬局・薬剤師にふさわしい内容の大阪府薬独自の研修会を考えていきたい。グループディスカッションの点数化も実施する」と説明する。
同制度の有効期限は2028年9月11日で、3年間は移行措置期間が取られる。「移行措置中は、大阪府薬の研修会単位を3単位取得すればそれ以外はどこの研修単位も認められる。移行措置期間終了後に新たな認定を受ける場合や更新(3年毎)時は、他の研修制度と同様に半数以上大阪府薬の研修会の単位が必要となる」(伊藤氏)
他方、2025年度地域医薬品提供体制構築推進事業について乾氏は、「昨年度の処方箋受取率は、全国で82%、大阪で74%と初期の目標の70%を達成している」と指摘。さらに、「我々は、しっかりと目に見える形で医薬分業の利点を患者さんに提供していると考えているが、中央の議論ではまだまだ十分その機能を発揮していないとの意見もある」とした上で、「医薬分業のメリットをしっかり示せるように地域医薬品提供体制構築推進事業に尽力したい」と訴えかけた。
同事業では、56支部毎に地域医薬品提供体制連絡協議会を設置する。協議会には、各地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会の代表、地域薬局連絡会の代表者を始め、訪問看護師、介護士、行政などが参画し、各地域に合致した医薬品提供体制の構築について検討を行う。
大阪府下の保険薬局4600軒の内、大阪府薬の会員薬局は3600軒強、非会員薬局は1000軒弱を数える。地域薬局連絡会は、非会員薬局も含めた全ての薬局によって地域医薬品提供体制を構築することを目的としたものだ。
各支部の地域医薬品提供体制連絡協議会では、「地域薬局機能の把握とリスト化」、「夜間・休日対応体制の整備とリスト化」、「地域の備蓄薬局リストの整備」、「在宅医療における薬剤師連携体制の構築」などが進められる。
その中で、薬局機能および夜間・休日体制については各支部で12月中に薬局のリスト化を行い、来年1月に大阪府薬に報告する。これらのリスト化や地域医薬品提供体制連絡協議会の運営費用は公平に分担し、地域薬局連絡会がその応分を非会員薬局から徴収する仕組みになっている。



