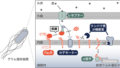臨床検査技師及び衛生検査技師の職能団体の日本臨床衛生検査技師会(東京都)は22日、会員向け広報誌JAMTマガジンが「変化していく臨床検査技師 AI時代に活躍できる臨床検査技」をテーマに開催した座談会のサマリーを公表した。
同座談会では、師臨床検査DXに携わる診断薬・医療機器メーカー2社も出席し、急速に進む臨床検査DX、変化していく臨床検査技師 AI時代において臨床検査技師の業務形態や役割はどう変化していくのかを、未来の臨床検査技師に期待される役割 、2040年問題(平成の30年間と、2040年にかけての社会の変容、令和2年度版厚生労働白書)も含めてディスカッションされた。
「医療DX」で国民にとって利便性があるのはマイナンバーやスマホアプリを通して電子カルテや患者情報などのデータを活用する厚生労働省が推進している行政サービスだ。
民間企業や医療機関などでは、超音波、MRI、CTなどの画像診断におけるAIの活用を「医療DX」と称している。現在、臨床検査におけるAI技術の活用は補助的な役割で、検体検査を実施するのは人間であるが、自動化・ロボティクス化で将来は無人に近い状況になると言われている。
検体検査の現場ではどこまでDX化が進んでいるのか
臨床検査技師が行う検体検査は、検体の採取(血液や尿など)、検体の前処理、測定、結果を解析して報告という流れで行われている。現在、採血などの検体の採取以外は、作業のDXまたはAIが活用されるようになってきた。
今後は、前処理もなくなり、測定と結果解析と報告がパッケージされた分析機械の登場も見込まれている。検体系の分析機械や画像の分析機械も同様であり、さらにデジタル化が進んでいくと考えられている。検体検査の全てがデジタル化されるのも遠い未来の話ではなさそうだ。
臨床検査DXの普及で臨床検査技師の役割はどうなる?
生産性向上を目指した業務の効率化において、デジタル技術や技術革新に任せられると判断できるところは任せて、きちんとしたデータ管理・品質管理ができるようになることが、臨床検査技師たちの役割だと考えられる。
デジタルを使って行う測定の精度管理、品質の担保、さらに検査結果に不足がないのかなどの点は、臨床検査技師の確認が必要である。特に、人手不足が指摘される地方の医療現場では、デジタルを活用した生産性向上はこの先、必須といっても過言ではない。
AIによる「新たな知見」の検査データへの付加が可能に
臨床検査においてAIの活用は、生産性があがるという点のほか、検査結果に基づき、膨大なデータと掛け合わせた解析を行うことで「新しい知見」を創出するという付加価値が提供できると考えられている。
このデータを提供することで臨床をサポートできるようになれば、医師からも頼られる臨床検査技師にもなり得る。「検査データ全般や、症状、薬理などの理解を深めることによって、医師の脇で診療の支援ができるようになる」のが目指すべき姿だと考えられる。
臨床検査技師の仕事はDXによってなくなってしまうのか?
「臨床検査DX」によって臨床検査技師の仕事はアウトソースされるのでは?という意見がでている。だが、AIはあくまでも“人の仕事をより良くする”のが目的であり、仕事のパートナーだと考えられる。そのためにも、臨床検査技師の意識・知識・技術レベルをもっと上げる必要がある。
生成AIが作成する解析結果をチェックでき、さらにそのデータの信憑性などを的確に分析する、それも得意分野だけに留まらず、さまざまなデータが一定程度読めることによって、初めて臨床に提供できると考えられる。
臨床検査技師は、医療においてデータサイエンスのプロになるべく、日本臨床衛生検査技師会も、それに対応する教育の必要性を感じている。
臨床検査DXを推進する際の課題
新しいデジタル技術を取り入れるにあたり、臨床検査技師の課題としては、日々接する情報量の少なさが挙げられる。専門知識をさらに深める、専門の幅を広げるということも、AI解析によるデータを活用し付加価値をつけた検査結果を導き出すために重要である。
加えて、「臨床検査DX」を推進するには、知識欲旺盛なスタッフを新しいチャレンジへと導く、イノベーションを起こしたいと考えて周囲を引っ張るリーダーシップなどのマネジメント力も不可欠である。
変化する医療の現場、臨床検査技師の活躍の場は検査室の外にあり
将来的には、スマホのツールなどを利用して症状から病気の可能性や治療、投薬まで、疾患を自己コントロールするといった構想があるそうだ。これは、2040年問題の対策としても考えられている。例えば、簡易検査機器が家庭に常備され、それで経過をみるという時代がくると、臨床検査技師の働き方を考える必要があり、在宅診療のチームに加わるという将来像もみえてくる。実際、臨床検査技師が在宅診療に帯同すると、医師は必要な検査を臨床検査技師に指示を出せば医師自身は患者の病状把握の問診に専念できる。
検査結果から必要な処置を訪問看護ステーションに指示を出し、後追いの形で看護師がケアに訪れることで、処置をする時間が削減され、医師が巡回できる件数も1.5倍になるというケースも考えられる。医療機関以外にも臨床検査技師は活躍の場が広がっていきそうだ。