
参天製薬は7日、3月9日~15日の世界緑内障週間に「緑内障の早期発見と治療の重要性を伝える啓発活動」を実施すると発表した。
参天製薬は、眼科に特化したスペシャリティ・カンパニーとして、眼の疾患や不具合に起因する世界中の人々の社会的・経済的な機会損失を削減するとともに、治療における利便性を
改善するなど、患者のQOL向上を日々追求しており、同イベントはその一環として実施するもの。各国・地域の活動内容は次の通り。
①日本

◆日本緑内障学会が実施する「ライトアップ in グリーン運動」への賛同
参天製薬は、日本緑内障学会が2015年より実施している「ライトアップ in グリーン運動」に、引きつづき賛同する。この運動は、緑内障の認知向上を目的として、公共施設や医療機関等の様々な施設を、緑内障のシンボルカラーであるグリーンにライトアップする運動である。より多くの生活者に情報を届けるべく、XおよびFacebook のアカウント「Santen目の健康情報室」と LinkedInを活用する。
また、国内の事業所および奈良研究開発センターや工場など50以上の拠点にて緑色にライトアップし、「ライトアップinグリーン運動」の認知拡大に協力する。
◆「おぐらなおみ」氏のインタビュー「緑内障の早期発見が美大受験のきっかけに」の公開予定
参天製薬の様々な活動をストーリー形式で紹介する「Santenストーリー」(コーポレートサイト)で、「おぐらなおみ」氏のインタビュー記事を公開する。記事では、「診断に至った経緯」や「診断を受け入れるまでの心境の変化」「治療に対する考えや重視していること」「治療を継続するうえでのモチベーションの保ち方」を聞き、定期的な眼科検診受診のの大切さを発信する。
② 中国

医療従事者と一般生活者を対象にしたチャリティランとオンライン講義を開催 中国では、医療従事者とともに、世界緑内障週間中にチャリティランを開催する。
テーマは「運動を通じた眼圧低下の促進」で、北京や温州など中国本土の10 都市で行い、各都市で100 名以上の参加者が見込まれている。
また、参天製薬は、医師と患者向けにオンライン講義も開催する。緑内障の理解を深め、早期発見を促進することを目的に、約30 回のセッションを予定している。
③ アジア
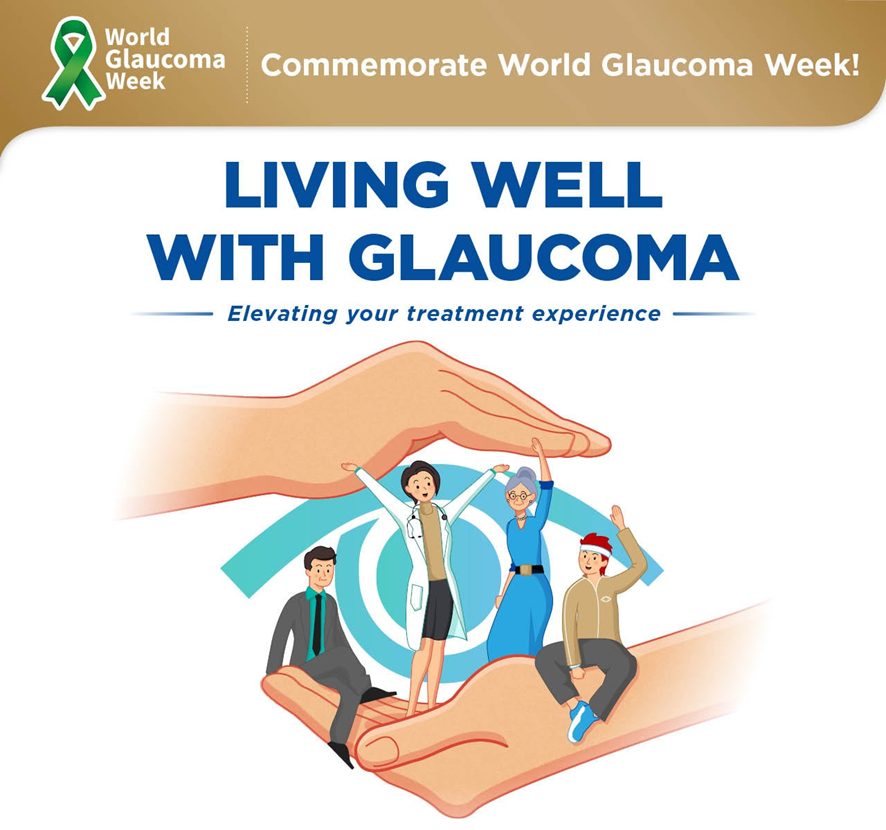
緑内障と共に生きる – 患者への情報発信を通じ治療体験の向上を目指す。今年の世界緑内障週間のテーマ「Uniting for a Glaucoma-Free World(緑内障のない世界に向け団結しよう)」は、早期診断から緑内障と共に健やかに生活することを支援するというSanten Asiaの使命と合致していることから、アジアでは、地域および現地の緑内障学会や患者団体と連携し、医療従事者を通じた有益な情報と支援を提供する。
緑内障患者向けに、疾患に関するリーフレットの配布や、啓発のためのスライド資料や動画、そして緑内障の認知を高めるためのソーシャルメディア投稿などを通じて、緑内障に関する新しい情報を提供するとともに、疾患管理の改善に向けた意識向上を目指す。
④ EMEA
疾患啓発を目的とした動画「Your Vision Is Your World2.0 – Hero Film」を公開
EMEAでは、緑内障患者が直面する課題に焦点を当てた独創的かつ感情に訴える取り組み「Your Vision Is Your World」を以前より展開しており、本年も疾患啓発を目的とした動画「Your Vision Is Your World2.0 – Hero
Film」を3月10日に公開する。
Santen EMEAは、「Your Vision Is Your World」の新たな試みを開始する。昨年好評を博した動画の出演者たちと再会し、アナザーストーリームービーを撮影した。ムービー内では、リバプール大学(イギリス)のNeeru Vallabh(ニール・ヴァラブ)先生をファシリテーターに迎え、緑内障が人生に与えた大きな影響について、出演者たちと振り返る。
この取り組みでは、患者の体験談を通して、「定期的な視力検査」と「視力低下、失明をおびやかすこの病気の早期発見の重要性」を訴え続ける。個人の体験を共有することで、「Your Vision Is Your World」は、患者と医師双方の橋渡しとなり、新たな共感の創出を目指す。
緑内障は、視野欠損につながる視神経の損傷を引き起こし、多くの国において視力低下や失明を含む視覚障害の主な原因となっている。この疾患は、一般に進行性で非可逆性であるため、早期発見・早期治療によって進行をコントロールすることが不可欠だ。
参天製薬は、日本をはじめとした中国、アジア、EMEA(Europe, Middle East and Africa)など、世界規模で緑内障の認知向上を図るとともに、早期発見に向けた定期的な眼科検診の大切さなど、積極的に情報発信をしていく。


