てんかん診療サポートシステムの社会実装を目指して
大塚製薬は3日、eMind、東北大学大学院医学系研究科(研究科長:石井直人氏)と「てんかんスマート医療共同研究講座(第Ⅱ期)」で、てんかん患者さん向けのスマートフォンアプリ「eMind for Medical Research」を用いた共同研究を開始したと発表した。
今後、てんんかん患者のQOL向上に貢献すべく、将来的には研究成果をもとに、テクノロジーを活用したてんかん診療をサポートするシステムの社会実装を目指す。

2021年には世帯保有率97%を超える普及率である情報通信機器、その中でも特に身近なデバイスであるスマートフォンやウェアラブルデバイスには、多種多様なセンサー・機能が搭載されており、その操作ログは、今や人の認知や行動と密接な関係にある。
2022年10月に設置された「てんかんスマート医療共同研究講座(第I期)」では、eMindが保有する、デジタルデバイスから得られるデータを用いたAIによる予測技術(特許 第6841466号)をてんかん分野に応用し、てんかん患者の身体的・精神的・社会的側面を支援することを目的に研究した。
2023年4月からは、東北大学病院のてんかん入院患者を対象に、入院精査期間中の各種生体信号・行動情報、心理社会的側面の評価データ、スマートフォンアプリ「eMind for Medical Research」による日常生活におけるデータを、AIにより解析することで、てんかん発作の予知や心理状態の推論モデルを研究し、身体的・精神的・社会的アセスメントと、その相関性に関する検証が行われた。
これらの研究活動を経て、昨年5月にはてんかん発作予測モデルに関する特許を取得(特許 第7534745号)し、現在国際出願中である。
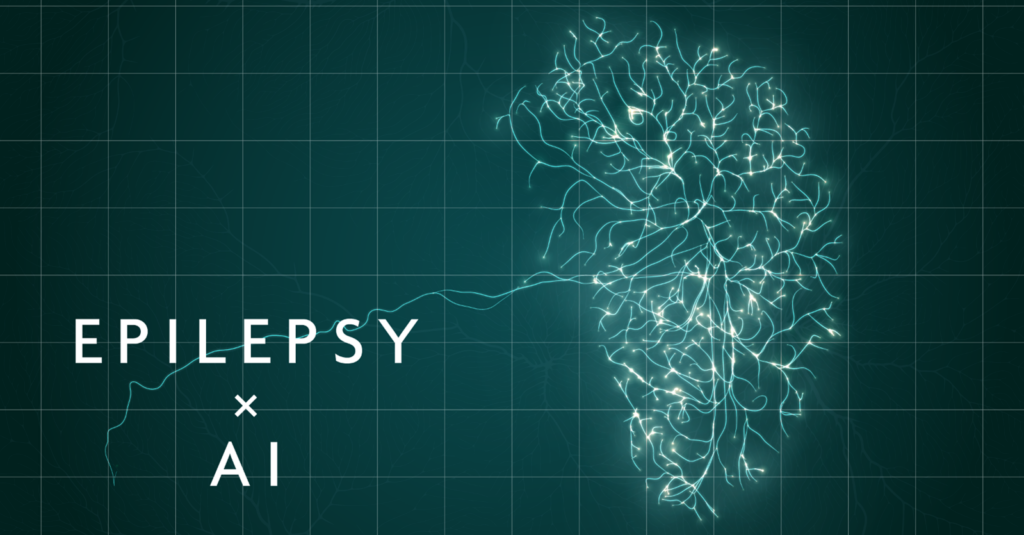
また、アプリ内機能「AnyTalk」では、てんかん患者さんの治療や服薬アドヒアランスの維持・向上を目的としたソーシャルサポートサービスを実施している。
利用者が日々の出来事に対する考えや気持ちを入力すれば、eMindが認定した有資格の心理サポーター(公認心理師/ 臨床心理士)から、心理学的知見に基づいた支持的・共感的なメッセージが返信される仕組みになっている。
利用者のQOL向上や孤独感・不安感にアプローチするものとして、患者から高い評価を得ている。こうした心理社会面での支援の有用性を評価・検証することも、社会実装に向けた具体的な取り組みの一つである。

2025年4月に、大塚製薬が「てんかんスマート医療共同研究講座(第Ⅱ期)」への参画が決定した。今回開始された第Ⅱ期研究は、第Ⅰ期の研究成果を踏まえつつ、大塚製薬のデジタルソリューション推進部門とも連携をしながら、より社会実装を視野に入れた応用研究活動を実施し、患者の体験価値向上を目指したシステムの継続的な開発・検証を推進。同研究の成果を元に、テクノロジーを活用したてんかん診療をサポートするシステムの社会実装を目指す。てんかんスマート医療共同研究講座の概要は、次の通り。
1、名称:てんかんスマート医療共同研究講座(第Ⅱ期)
2、目的:デジタルデバイスとAIにより、てんかん患者の身体的・精神的・社会的側面を支援しQOL向上に貢献する
3、研究代表者:東北大学大学院 医学系研究科・教授 遠藤英徳氏、eMind 取締役COO 古村智氏、大塚製薬ポートフォリオマネージメント室 大西弘二氏
4、研究実施場所:東北大学
5、設置期間:2025年4月から2028年3月


