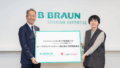2023年、認知症の人達との共生社会実現を推進するための「認知症基本法」が成立。翌24年には基本法に基づく「認知症施策推進基本計画」を閣議決定して、“認知症の人が尊厳を持って地域で暮らし続ける社会の実現”を目指している。
こうした背景の下に第58回日薬学術大会では、「薬剤師による認知症ケアの新展開」をテーマとした分科会が企画された。分科会では、最新の認知症施策、薬物療法の動向、非薬物療法のエビデンス、薬剤師が現場で果たすべき役割などについて多角的な議論を展開。「薬剤師も現場で認知症の人と接してその声を取り込んでいく」重要性や、「向精神薬投与後の患者の具体的な状態を医師に伝えて適正な処方をするためのアシストをしていく」方向性が確認された。
また、認知症の人のポリファーマシー対策推進において、掛かり付け薬剤師の役割が大きなポイントになっており、今後、疾患修飾薬時代に対応した認知症薬物療法のパラダイム転換の中心に薬剤師を位置づけるよう要望された。
分科会の中で遠坂佳将氏(前厚労省老健局認知症施策・地域介護推進課)は、「共生社会の実現に向けた認知症施策の推進」について講演した。
認知症の高齢者は日本で急増しており、100人に30人が認知症のリスクを抱え、認知症を「我がこと」と認識する時代がやってきた。こうした現況において、「地域の中で認知症を支える」、「新しい治療薬の開発」が注目されている。
遠坂氏は、「認知症と共にどのように生きていくかが社会課題である」と強調する。認知症基本法は、①共生社会の実現、②認知症の人の基本的人権の共有③認知症の人やその家族の意見を聞いた上で計画を策定するーを理念としている。
また、新しい認知症観として「認知症になったら何も出来なくなるのではなく、認知症になってからも一人一人が個人としてできること、やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間らと繋がりながら“希望を持って自分らしく暮らし続ける”ことができる」という考え方が提唱されている。
遠坂氏は、認知症施策の基本計画を起点とした具体的な施策として、「認知症カフェ」、「ピアサポート活動」、「本人ミーティング」、「認知症希望大使」、「認知症の人の社会参加」を挙げた。
認知症カフェは、認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有してお互いを理解し合う場で、全国に8558箇所存在する。
ピアサポート活動は、認知症の人が認知症の人の相談を支援する活動で、認知症の人の社会参加を後押しするものだ。
本人ミーティングは、認知症の人が集い、中心になって自らの体験や希望、必要としていることを語り合い、自分達のこれからのより良い暮らし、地域のあり方を一緒に話し合い、発信していく場である。
認知症希望大使は、厚労省から7名の認知症当事者を任命し、国が行う認知症啓発活動への参加や協力、国際的な会合に参加する。
認知症の人の社会参加は、介護サービス事業所が介護サービスの提供時間中に認知症の人が地域住民と交流したり、公園の清掃活動や企業と連携した有償ボランティア等の社会参加活動の取り組みを進める。
「認知症施策推進基本計画は、認知症の人と出会って意見を聞くことが大きなポイントになっている」と改めて断言する遠坂氏。その上で、「薬剤師も現場で認知症の人と接してその声を取り込んで、ポリファーマシー対策を推進するための掛かり付け薬剤師としての役割を発揮してほしい」と要望した。
遠坂氏は、早期アルツハイマー病治療剤「レケンビ」にも言及。「認知症を完治するものではなく、進行を抑制するものである」と解説した。さらに、「認知症の初期とMCIの段階で、しかもアルツハイマー型のみの適応なので、完全なゲームチェンジャーにはなっていない」と説明した。
加えて、「この薬剤の登場により、認知症早期発見をより重要視する認識が高まったことは大きい。早期発見のための血液バイオマーカーの開発が日米で進められている」と現況を報告した。

成本迅氏(京都府立医大大学院医学研究科)も、レカネマブについて、「MCIの段階においても、『まだ必要としない』という認知症当事者は少なくない。一方、家族は薬剤に対する過度な期待がある」と医療現場の傾向を伝え、「その人の理解力・判断力に応じた情報提供が重要である」と強調した。
さらに、「病院での薬の説明は時間の制限があるため、患者、家族の意思決定支援服薬アドヒアランスの向上支援を是非薬剤師のみなさんにサポートしてほしい」と呼びかけた。
また、アルツハイマーでは妄想、興奮、血管性認知症では感情失禁、意欲の低下、レピー小体認知症では幻覚が多く見られる。認知症にはこうした様々な精神症状が伴うため、向精神薬、睡眠薬、抗不安薬、抗うつ薬など様々な薬剤が投与される。
成本氏は、「認知機能障害+精神症状が加わることで、非常に生活機能レベルが低下する。少しでも薬物治療等で緩和することが重要ではあるが、医師は投与した薬剤をきちんと評価しながら、効果が無ければその薬は止めたいと考えている」と明言し、「薬剤を投与して、今、どのような状態になっているのかを的確に把握するサポートも薬剤師さんにお願いしたい」と訴えかけた。
また、ブレクスピラゾール(抗精神病薬)が保険適用になったことにも触れ、「安心して認知症患者に処方できる。今後増えてくると思う」と語った。
「エビデンスから考える認知症の非薬物療法」をテーマに講演した木下彩栄氏(京大大学院医学研究科)は、WHOが認知症リスク低下の14因子として、「幼少期:教育歴、中年期:難聴、高LDL血症、うつ、頭部外傷、身体不活発、糖尿病、喫煙、高血圧、肥満、過度の飲酒、老齢期:社会的孤立、大気汚染、視力障害」をガイドラインに掲げていると紹介。
さらに、「高血圧症、糖尿病、高脂肪食摂取では、動物でもヒトにおいても、アルツハイマー発症と関連するAβ(アミロイドβ)の排泄に影響を及ぼすことが判ってきた」と解説した。
また、「非薬物療法はエビデンスが少ないものが多く、運動療法はエビデンスが集積している」とした上で、「その一方で、近年では認知症の予防において世界的に全般的な生活改善を目指した指導の有効性が注目されるようになってきた」と語った。
わが国でも、神戸大学が、兵庫県伊丹市において認知症予防を目指した多因子介入によるダンダム化比較研究を実施している。同研究では、運動、認知機能トレーニング、栄養管理、生活習慣病の管理から成る複合的な介入プログラムを週に1回90分、118ヶ月間継続することによって、高齢者の認知機能が改善した。
木下氏は、「イギリスで行われた研究で、帯状疱疹ワクチンが認知症は症リスクを2割低減した」ことも紹介した。