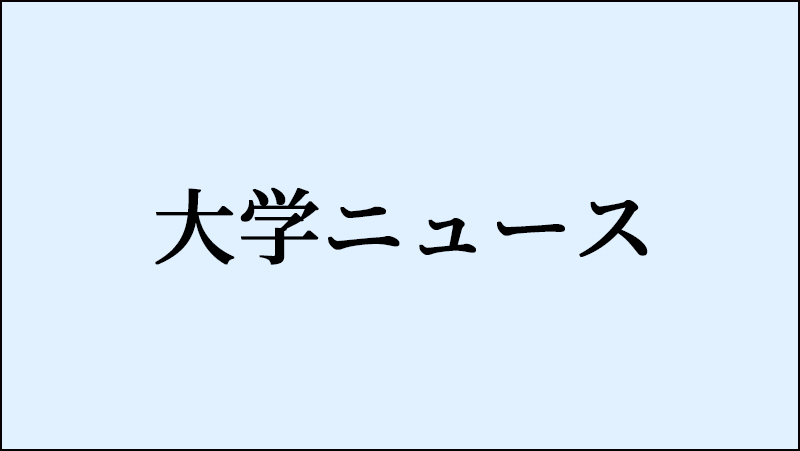大学院生命科学研究科の木村郁夫教授とNOSTER(本社:京都府)などの共同研究グループは、過剰な糖分摂取による肥満の抑制に関連するヒトの腸内細菌として「S. salivarius」を特定した。
S. salivariusは、摂取した炭水化物中の過剰なスクロース(砂糖)を、有益な食物繊維様物質である難消化性菌体外多糖(EPS)に変換し、宿主の糖吸収を抑制することが判明した。
今回の発見は、肥満や糖尿病などの代謝性疾患の予防や治療に新しいアプローチをもたらすものであり、EPSやEPS産生菌が腸内環境を改善することで、スクロース誘発性肥満を防ぐ可能性が期待される。同研究成果は、2025年1月29日に国際学術誌「Nature Communications」にオンライン掲載された。
高脂肪・高糖分の摂取は宿主のエネルギー恒常性を崩し、肥満を引き起こす。特にスクロース(砂糖)の摂取量増加は、世界的な健康問題となっている肥満や糖尿病などの主要なリスク要因とされている。
また、微生物もこれらの糖をエネルギー源として利用するが、ヒトとは異なる代謝経路を使用し、短鎖脂肪酸を生成する。特に、発酵性食物繊維(難消化性食物繊維)は効率的に短鎖脂肪酸を産生し、宿主のエネルギー代謝や内分泌系に影響を与えることが報告されている。
同研究では、腸内細菌が糖から難消化性多糖を生成し、宿主に代謝的利益をもたらす可能性に着目し、EPS産生ヒト腸内細菌の探索とプレバイオティクス効果の関係、さらに微生物代謝物が宿主の健康に与える分子機序の解明に挑んだ。
約500名のヒト糞便を用いたスクリーニングにより、高EPS産生菌として 5菌種を同定した。その中でも、S. salivarius はヒト腸内に広く存在しており、その占有率および短鎖脂肪酸濃度がBMIと負の相関を示すことから、ヒト腸内細菌由来EPS産生菌として S. salivarius に着目した。
SsEPSの構造解析とSsEPSを利用可能な菌の探索
S. salivarius がスクロースを基質として産生するEPS(SsEPS)の構造を解析した結果、ヒトが消化できない食物繊維様物質である難消化性多糖であることが判明した。加えて、ヒト腸内細菌優先菌種の単一培養により、Bacteroides属細菌がSsEPSを利用し、短鎖脂肪酸を産生することが確認された。
SsEPS摂取による代謝改善効果の検証
肥満モデルマウスにSsEPSを摂取させた結果、対照群に比べて体重増加が抑制され、腸内環境の変化、短鎖脂肪酸濃度や血糖値などの代謝能の改善が見られた。特に、短鎖脂肪酸を認識する受容体欠損マウスでは、これらの効果が消失したため、SsEPSによる代謝機能改善には短鎖脂肪酸が関与していることが確認された。
さらに、無菌マウスにSsEPS産生菌や資化菌(Bacteroides属菌)を移植したノトバイオートマウスを用いた実験からも、生体内でのEPSや短鎖脂肪酸の産生が確認されている。
これらの結果から、SsEPS産生菌が腸内で糖吸収を抑制し、EPS資化菌が生成した短鎖脂肪酸によってスクロース誘発性肥満を防ぐ一連のメカニズムを明らかになった。
同研究では、S. salivariusを抗肥満のバイオマーカーとして位置づけ、宿主の代謝機能への影響が明らかにされた。特に、S. salivariusが産生する難消化性の菌体外多糖(EPS)は、腸内環境を整え、短鎖脂肪酸の生成を促進することで、代謝性疾患の予防に寄与する可能性がある。
これらの知見は、腸の健康と代謝バランスを向上させるプロバイオティクスや機能性食品の開発につながる重要なものだ。また、S. salivariusの特性と有益な代謝物を活用することで、肥満や糖尿病に関連する代謝性疾患に対する予防や治療に対する新たなアプローチが可能になると考えられる。
さらに、近年では腸内細菌代謝物を摂取することで、健康増進をはかるポストバイオティクスにも注目が集まっており、ポストバイオティクス成分としてのEPSの効果も期待される。