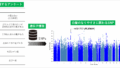滋賀医科大学と住友ファーマは14日、共同研究講座「創薬トランスレーショナル研究講座」の基本協定書締結式を実施した。同講座の開設は、アカデミアと企業の連携によって非ヒト霊長類(サル)を用いたトランスレーショナルな高次脳機能評価技術の構築と神経領域創薬への応用を通して、アルツハイマー病など難治性神経疾患の治療法開発に貢献することを目的としたもの。より実効性の高い神経領域の創薬目指して、本年10月1日に滋賀医科大学に設置された。同大学における11個目の共同研究講座となる。
精神・神経領域には、満足な治療法が確立されていない疾患がたくさんある。急速な高齢化において、精神・神経領域のメディカルニーズはますます高まっているものの、同領域の創薬は他の領域に比べて成功例が少ない。その要因の一つに、動物モデルで得られた薬効がヒトにおいて再現されないトランスレーション性の低さが指摘され、大きな課題となっている。
こうした中、高次な脳の研究を推進するには、ヒトと脳の構造や機能が近いサルを用いた脳機能評価技術のプラットフォーム(薬物脳波評価、脳血流測定、AI を利用した行動解析、およびニューロモジュレート技術を含む)の構築が不可欠となっている。
滋賀医科大学は、神経難病の研究を強みとしており、世界で有数のサルの遺伝子組み換え技術も有している。一方、精神・神経領域を重点研究分野の一つとする住友ファーマでは、2010年から非ヒト霊長類の活用に着目した前臨床研究を推進しており、サルの脳波測定、行動薬理等において優れた技術を有する。
サルを用いた脳機能評価技術のプラットフォーム構築には高い専門性が求められるため、滋賀医科大学と住友ファーマがお互いに研究技術を共有することでさらなる研究の進展、ひいては難治性疾患の治療法の開発が期待される。創薬トランスレーショナル研究講座の実施内容、構成員、住友ファーマ(SMP)、滋賀医科大学のそれぞれの役割は、次の通り。
【実施内容】
・SMP/公知化合物評価(BM、薬効、副作用、差別化)
・医療デバイス研究
・新たな脳機能評価技術構築
・神経疾患の病態モデル作製
【構成員】
・講座教員/特任教授1名 池田和仁氏(常駐)
・研究員5名登録(非常勤)
・飼育技術員(派遣)2名
・庶務(非常勤)1名
(共同研究費で雇用)
【住友ファーマ】
①共研費、②実験技術、③実験機器、④実験動物(アカゲザル36頭)の提供。化合物/デバイス評価結果(BM、薬効、副作用、差別化)、評価技術の拡充、特許出願。
【滋賀医科大学】
実験室、ラボオフィス(BMIC)、NHP飼育室の提供。飼育/実験技術支援、他講座提携機会、研究者教育、学術貢献(学会・論文発表)、特許出願、医薬品開発のノウハウ拡充。
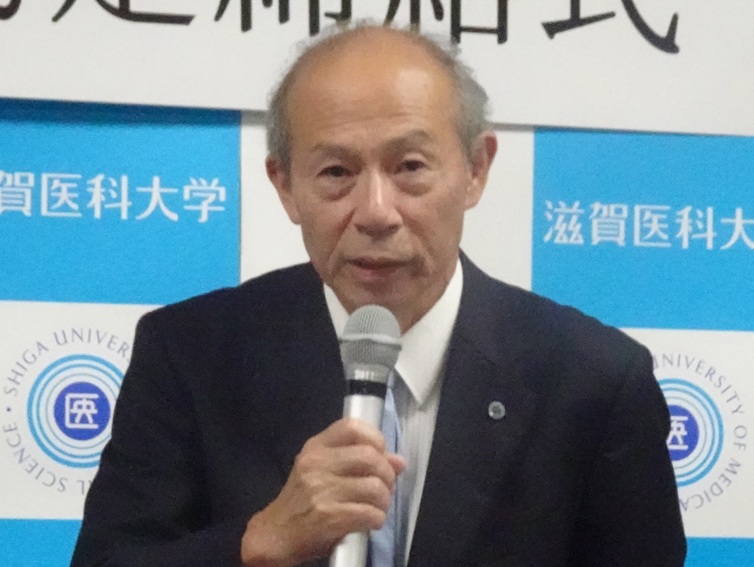
共同研究講座設置に関する協定締結式では、上本伸二滋賀医科大学長が、「非臨床試験から臨床への橋渡し研究を推進するため、医薬品評価、技術プラットフォームを整備し、創薬研究に貢献したい。また、滋賀医科大学の既存講座との連携を進め、新たな研究課題の創出を目指す」と強調。
さらに、「住友ファーマの注力分野の一つである精神・神経領域の創薬研究と、滋賀医科大学の神経難病研究やサルの遺伝子組み換え技術など双方の連携による新たな研究成果が期待される」と訴求した。

木村徹住友ファーマ代表取締役社長は、「当社が進めてきた非ヒト霊長類を用いた脳機能の基礎研究は、世界的にも高いレベルであると自負している」と明言。その上で、「こうした研究を発展継続するためには、アカデミーとの産学研究が不可欠である」と強調し、「単なる薬効評価に留まらず、精神神経疾患の病態メカニズムの解明やバイオマーカーの探索など、基礎研究と応用研究の橋渡しとなる研究を推進したい」と抱負を述べた。
池田和仁創薬トランスレーショナル研究講座特任教授は、「サルを用いた研究により従来の動物モデルでは再現の難しかったヒトに近い認知機能などのメカニズムを成実に捕らえることで、神経疾患の新たな治療法の開発に貢献したい」と語った。