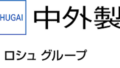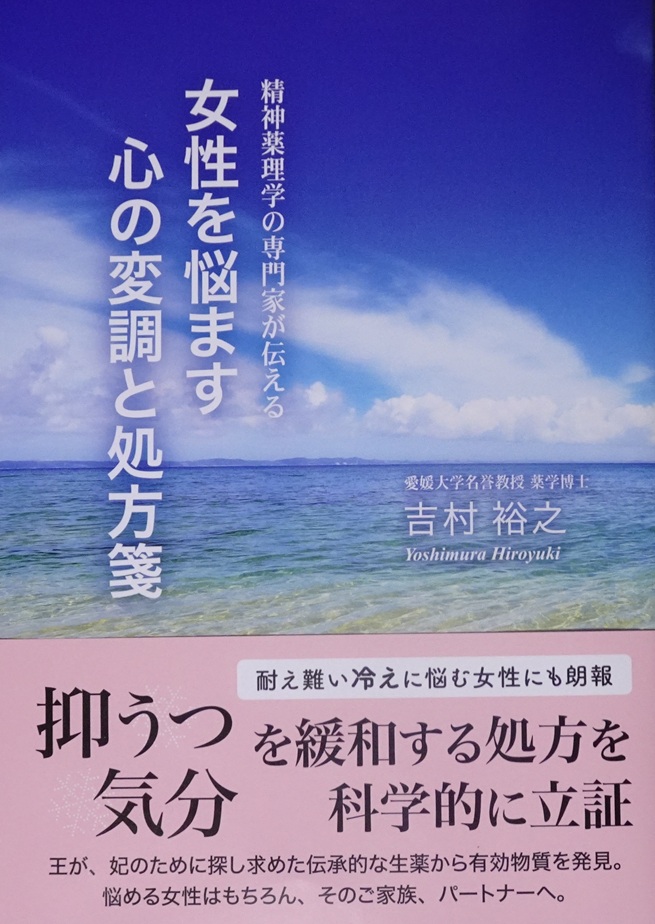
女性ホルモンは、生殖器以外に脳の機能を含め、脂質や骨の代謝、毛髪などほぼ全身で非常に多くの生理的役割を担っている。その分泌量の変化は、女性の心に色々な変調をもたらし、生活の質そのものを変容させる可能性がある。
齢を重ねるごとに、卵巣の機能は徐々に確実に衰えていき、卵巣で作られる女性ホルモンの分泌量も徐々に減少していく。その結果、女性の誰もが「閉経周辺期の自覚症状」を経験するようになる。やっかいなことに日本人は、この閉経周辺期が欧米人に比べてかなり長いとされ、しかも早くから始まる傾向がみられる。
思春期から閉経に至るまで、女性ホルモン分泌量の変動は、女性を悩ませる心の変調と密接な関係がある。思春期の月経緊張症や摂食異常(拒絶や過食)に始まり、閉経周辺期の倦怠感、無気力と実に多彩な症状を惹起する。
閉経周辺期の症状の惹起が女性ホルモンの枯渇化が原因ならばそれを補うという単純な発想のもと、ホルモン補充療法が閉経後の骨粗鬆症や動脈硬化症の予防を目的として、北米を中心に1992年頃から臨床的に適用された。
だが、女性ホルモンの変動に伴うさまざまな愁訴に対しても広く汎用されたため、長期連用による乳がんや生殖器がんの発症率が増加するという有害報告が相次ぐようになった。特に、2002年にホルモン補充療法の有効性確認を目的とした北米での大規模臨床試験において、有効性より危険視を警告する結果が示され、天然物や食物による代替医療に対する関心が高まるようになった。
そこで同書では、こうした天然物にも着目し、これまで焦点があまり当てられてこなかった心の変調、特に女性が陥りやすい抑うつ気分や抑うつ状態を緩和する科学的に立証された物質(処方)について詳しく紹介している。
抑うつ状態は、①女性ホルモンの分泌と密接な関係がある、②女性が男性に比べて2~3倍も発症率が高い、③臨床的な抑うつ状態には性差がみられる、④抗うつ薬の効果が男性と女性では異なるーなどの事項がこれまでに指摘されてきた。
だが、医薬品開発における基礎実験では、殆ど雄の動物のみが用いられ、雌の動物は「性周期による内分泌系の変動が得られた結果の理解を複雑にする」との思い込みから避けられてきた。すなわち、抑うつ状態が女性に多いにも関わらず、抗うつ薬の候補物質の殆どが雄の動物を用いて選別されるという矛盾があった。
これまで、抗うつ薬候補物質の選別試験として「強制遊泳法」が広く利用されてきた。険悪な状態から逃げることも避けることもできず、対処することもできない時、ネズミなどの齧歯類からヒトを含めた霊長類に至るまで、動物は種を超えて「動かなくなる(不動化する)」。
強制遊泳法は、足が届かない程度の深さまで水を満たした円筒形のガラス容器にマウスやラットを入れて、もがいたり、泳いだり、逃れるために壁をよじ登るなどの行動をした後に、逃げられないことを学習して顔だけを水面に出して浮遊し、動かなくなる(行動的絶望)までの不動時間を観察する動物実験である。
現在、臨床的に使用されている殆どの抗うつ薬は、この不動時間を短縮する効果があり、絶望感を緩和して抑うつ状態を改善すると考えられている。ただし、雄の動物を用いた実験結果であるため、筆者らは、雌の動物の卵巣を摘出することにより人為的に閉経させ女性ホルモンを枯渇させた新たな動物モデルを作成して、遊泳法の不動時間の延長を同定。女性ホルモンの減少が抑うつ状態の発現機序に重要な役割を果たしていることを確認した。
さらに、この動物モデルへの女性ホルモン(エストラジオール)や、抗うつ薬の投与により不動時間の延長減少が短縮されることを見出した。
同書では、雌の動物の卵巣を摘出した抑うつ状態の新たな動物モデルを使用して、古くから伝承的に抑うつ状態の改善に使われてきた天然物の有効性を確認し、その有効物質を分離・精製して化学構造を明らかにした上で抑うつ状態を改善する天然物を紹介している。
また、冷え性の女性を識別するための指標を初めて科学的に立証し、冷え性に有効な天然素材を公表しているのも興味深い。
「女性を悩ます心の変調と処方箋」は、第1章:女性ホルモンの分泌と心の変調、第2章:閉経周辺期とは、第3章:閉経周辺期の自覚症状を測定するには?、第4章:抑うつ気分と抑うつ状態、第5章:抑うつ状態を緩和するには?、第6章:精神機能に及ぼす効果を評価するには?、第7章:抑うつ状態を雌動物に起こさせるには?、第8章:抑うつ状態を改善する天然物は?、第9章:耐え難い冷えに悩む女性に、第10章:冷えに効く天然物は?ーの10章で構成している。定価は1800円+税。